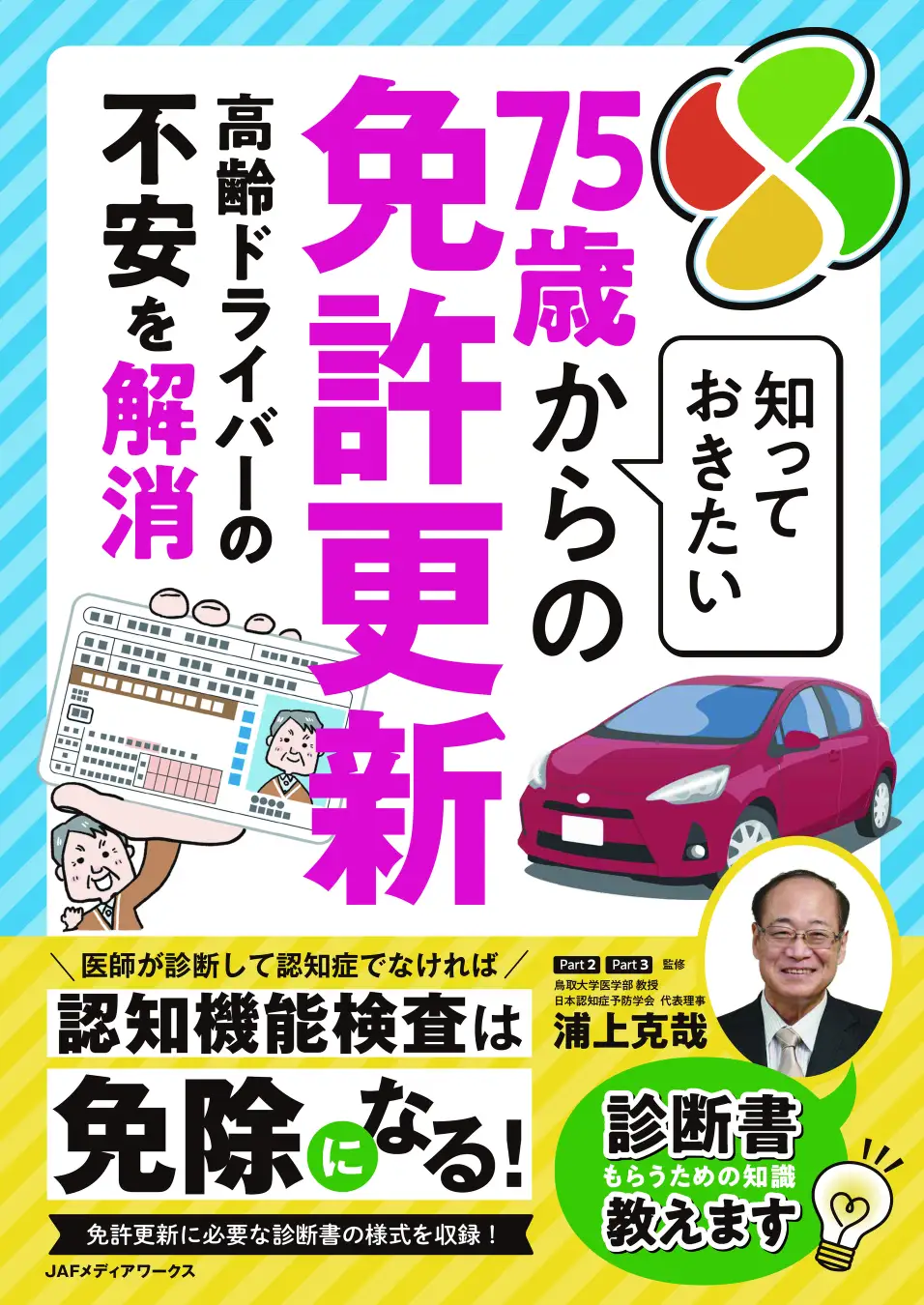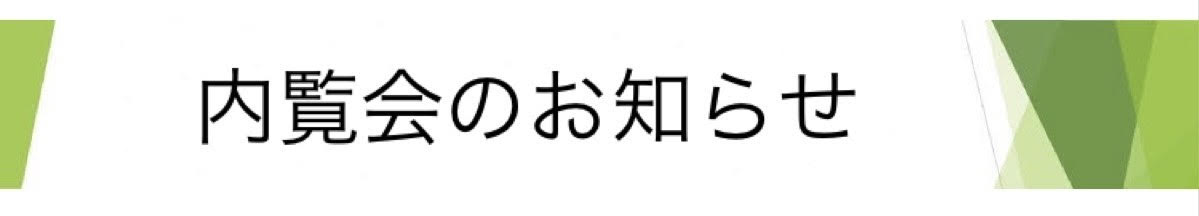一人暮らしに不安はつきもの。特に防犯面では、自分の身を守る意識が大切です。この記事では、シニア世代が安心して暮らすための防犯対策を、「日々の習慣」「防犯設備」「人とのつながり」の3つの視点から解説します。
高価な機器に頼らなくても、防犯性は高められます。今日からできる簡単な工夫など、安全で快適な一人暮らしを実現するヒントが満載です。
まず見直したい防犯意識と暮らし方
防犯というと、つい高額な警備システムや最新機器を想像しがちですよね。しかし、実は日々のちょっとした「無意識のクセ」や「習慣」が、思わぬスキを生んでしまうこともあるんです。
まずは、特別な準備をしなくても、今日からすぐに始められる行動のポイントから見直してみましょう。
①戸締まりは「無意識のまま」やらない
玄関を出た後、「あれ?鍵、閉めたかな?」と引き返した経験はありませんか?
戸締まりは毎日の習慣だからこそ、無意識のまま行ってしまいがちです。こうした“うっかり”が、空き巣に狙われるきっかけになることもあります。
【うっかりを防ぐ!鍵のかけ忘れ対策】
- 指差し声出し確認
- 外出前の最終チェック
- 就寝前の戸締まりタイム設定
鍵を閉めたら「よし、閉めた!」と声に出す「指差し声出し確認」を習慣にしましょう。
また、出かける前には「玄関・窓・ガス元栓」など、必ず目視で確認する「外出前の最終チェック」も忘れずに。さらに、スマホなどでアラームをセットし、就寝前に「戸締まりタイム」として確認を促すのも有効です。
無意識の行動を意識的な習慣に変えるだけで、ご自身の安心感も、住まいの防犯レベルも大きく向上します。
②突然の来訪者に“反射的に出ない”
ピンポンが鳴ると、つい反射的にドアを開けてしまう…そんな経験はありませんか?
しかし、それが悪質な詐欺や強引な訪問販売のきっかけになってしまうケースが後を絶ちません。
大切なのは、「誰が来たのか」を冷静に判断し、「出ない」という選択肢を迷わず選ぶ「勇気」を持つことです。
【悪質業者から身を守る!訪問者対応の鉄則】
- モニター付きインターホンで顔を確認
- 宅配は心当たりのないものに応じず、置き配活用時はすぐに回収
- 「家族からのアポなし訪問は応じない」マイルールを設定する
ドアを開けずにモニター越しに相手をしっかり見極めるモニター付きインターホンは、不審な来訪者対策に必須の設備です。まったく身に覚えのない宅配は受取拒否をしましょう。「置き配」も有効ですが、盗難やいたずら防止のため、届いたらすぐに取り込むことが大切です。
また、家族であっても「アポなし訪問は応じない」といったマイルールを設定し、不審な来訪者はドアを開けずに家族に確認する習慣をつけましょう。
「断るのは申し訳ない」「無視するのは失礼なのでは?」と思う必要は全くありません。ご自身の安全を守る上で、“出ない勇気”こそが、最も効果的な防犯対策なのです。
設備で備える!安心を支える防犯ポイント

日々の行動の見直しとあわせて、「設備」で備えることも大切です。特に一人暮らしの場合、自分で守れる範囲には限界があります。ここでは、大掛かりな工事をしなくても比較的簡単に取り入れられる防犯設備をいくつかご紹介します。
①夜間の玄関や廊下は「人感ライト」で防犯+安心
夜間の玄関や廊下の暗さは、不審者リスクだけでなく、転倒の危険も高めます。そこで活用したいのが、人の動きで自動点灯する「人感センサーライト」です。
これは不審者への「威嚇効果」が高く、帰宅時や移動時の足元を明るく照らし、転倒事故も防ぎます。最近は賃貸住宅での標準装備や、ホームセンターで安価な後付けタイプも増えているので、ぜひ積極的に検討してみましょう。
②鍵とドア周りの「防犯力」を見直す
泥棒の約7割は侵入まで5分かかると諦めるというデータもあります。また、侵入した家を選んだ理由の1位は「クレセントを外せば入れるから」という調査結果からも、玄関ドアの鍵や構造が脆弱だと、あっという間に侵入されてしまう危険性があるのがよく分かります。ご自宅のドア周りは大丈夫でしょうか?
【玄関の防犯力を高める3つのポイント】
- ピッキングに強い「ディンプルキー」の確認
- 「ワンドア・ツーロック」で防犯性を強化
- チェーンより頑丈な「ストッパー付きドアガード」
従来のギザギザした鍵と異なり、表面にくぼみが複数ある「ディンプルキー」は、ピッキングに非常に強く、解錠に時間がかかるため泥棒に狙われにくいのが特徴です。
また、一つのドアに鍵が複数ある「ワンドア・ツーロック」は、侵入時間を長引かせ、諦めさせる効果が期待できます。
内側から後付けできる補助錠も検討してみましょう。さらに、従来のドアチェーンより頑丈な「ストッパー付きドアガード」は、不審者の押し入りを防ぐのに役立ちます。
お住まいの鍵やドア周りの防犯力が気になる場合は、賃貸物件なら管理会社に、持ち家なら専門業者に相談してみるのがおすすめです。
③カメラ付きインターホンで訪問者を見極める
不審な来訪者対策に最も効果的なのが、カメラ付きインターホンです。ドアを開ける前に相手の顔や様子をモニターで確認できるため、知らない人や怪しいと感じる人には、ドアを開けずに対応できます。
「見てから判断できる」安心感は、シニア世代にとって特に大きなメリットです。スマホ連携や録画機能付きなど、進化した製品も増えており、より安全な暮らしを支えてくれます。
人とつながることも防犯の一歩
どんなに自宅の防犯対策を徹底しても、「一人ですべてを守る」ことには限界があります。いざという時、頼れる人がいる。この「つながり」こそが、実は最も心強い防犯対策になるのです。
離れていても「定期連絡」で安心
一人暮らしだからこそ、誰かと「つながっている」という安心感が、精神的な支えだけでなく、最大の防犯対策になります。離れて暮らす家族や親しい友人との定期的な連絡は、もしもの時の早期発見につながります。
【離れて暮らす家族も安心!見守り連絡のコツ】
- 「毎週〇曜日は電話の日」と決めて習慣化
- 万が一のための「3日連絡なしルール」を共有
曜日や日にちを決めて連絡を習慣化する「定期的な連絡習慣化」は、互いの安心につながります。また、万が一に備え、「3日連絡がなかったら安否確認する」といった「連絡なしルール」を共有しておくのも良いでしょう。
最近では、安否確認や緊急時の駆けつけサービスを提供してくれる「見守りサービス付き賃貸住宅」も増えています。離れていても、温かい「つながり」を感じられる方法はたくさんあります。
自治体や地域の見守りサービスを活用
自治体や地域には、一人暮らしのシニアの方々を支える、心強い「見守りサービス」が数多く用意されています。すべてを自分一人で抱え込まず、こうした公的な支援を積極的に活用することで、防犯のセーフティネットを広げることができます。
- 「緊急連絡カード」の活用
- 民生委員・地域包括支援センターの定期訪問
- 郵便・電力会社などとの連携協定
地域の民生委員や地域包括支援センターなどで配布されている「高齢者見守りシール」や「緊急連絡カード」は、ご自身の健康状態や緊急連絡先などを記入しておく大切な情報源です。いざという時にすぐにわかる場所に保管しておきましょう。
また、民生委員や地域包括支援センターは、地域の高齢者の生活を多角的に支援する役割を担っており、定期的な訪問を通じて困りごとの相談や情報提供を受けられます。
最近では、郵便局員や電力会社の検針員などが訪問時に異変を察知した場合に自治体へ連絡するといった「郵便・電力会社などとの連携協定」が結ばれている地域もあります。
「地域の皆さんに見守られている」という感覚が、不安を和らげ、毎日の安心につながります。積極的に情報を集め、活用していきましょう。
防犯性の高い住まいを選ぶのも大事な備え
日々の「行動」、頼りになる「設備」、そして温かい「人とのつながり」。これらの防犯対策を全て一人で完璧にこなすのは大変かもしれません。だからこそ、「最初から安心できる住まい」を選ぶという選択肢も、非常に賢い防犯対策の一つとなるのです。
近年、オートロックや防犯カメラ、人感照明、カメラ付きインターホンといった設備が充実した「シニア向け賃貸住宅」が増えつつあります。また、安否確認や生活支援サービスがある物件なら、もしもの時も安心です。
防犯面でも安心して暮らせる住まいをお探しの方へ
- 今の家では防犯が少し心配。
- もっと安心して、気兼ねなく一人暮らしを続けたい。
- 離れて暮らす家族にこれ以上心配をかけたくない。
もし、このような不安を抱えているなら、防犯設備が整ったシニア向け賃貸住宅の検討をしてみるのも一つの方法です。オートロックやモニター付きインターホン、防犯カメラ完備はもちろん、24時間の緊急対応や見守りサービス付きの物件も豊富にあります。
⇒ 「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」その魅力とは?
⇒ 積水ハウスグループの自立型サ高住「グランドマストシリーズ」その魅力とは?
ご自身にとって最適な「安心・安全な住まい」を見つけるために、まずは情報収集から始めてみませんか?
防犯面から見たシニア向け賃貸の選び方については、こちらの記事を参考にしてください。
⇒ 防犯設備で選ぶシニア向け賃貸|オートロック・カメラ・鍵のポイント
※空室状況は変動するため、個別ページへの直リンクではなく検索ページにご案内します。
参考:警視庁「住まいる防犯110番」
(グッドライフシニア編集部)