
介護保険制度による介護サービスを利用するには「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護・要支援認定とは、被保険者が介護を要する状態であることを保険者である市町村が認定するもので、手続きや受けられるサービスの内容も違います。
では、要介護認定を受けるためにはどのように手続きを進めれば良いのでしょう。
要介護認定の申請から認定後までの流れについて分かりやすくご説明していきます。
1.要介護・要支援認定を受けるための申請方法
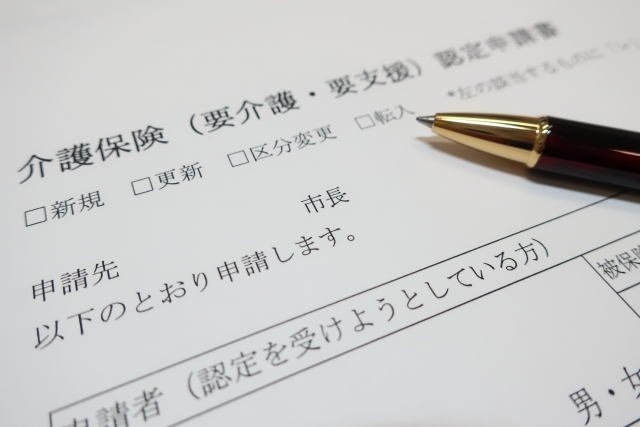
認定を受けるには、市区町村の窓口で「要介護・要支援認定」の申請をします。
一次認定の際には、調査員が自宅に訪問し細かい項目についてアンケートをとっていきます。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書も作成してもらいます。
介護認定調査で聞かれることを知っておきましょう。事前に準備して実際よりも低い要介護度にならないために、普段の様子をしっかり伝えるようにしてください。
詳しい調査内容や押さえておきたいポイントはこちらの記事を参考になさってください。
■介護認定調査は何をするの?事前に知っておくべきこと ~親の自尊心も大切に~
認定までの手順
介護サービスをどれくらい必要としているかを客観的に、かつ公平に判定するため、コンピュータによる1次判定と、それを元に保健医療福祉の学識経験者が行う2次判定の2段階の方法で行います。
STEP1 市区町村への申請
各市町村には介護保険課などがありますので、要介護認定の申請に行きましょう。まずはお住まいの市町村の窓口に、要介護認定の申請に必要な書類や注意事項などを聞いてみましょう。書類の提出先は同じく、各市町村の担当窓口です。
STEP2 要介護認定の訪問調査
各市区町村の職員または委託されたケアマネージャーなどの認定調査員が実際に家庭を訪問して、どの程度の介護が必要か心身の状況を聞き取り調査します(認定調査)。
訪問調査の際は必ず家族の同席が必要です。そして、主治医による意見書も必要なので、介護保険を申請する方の心身の状況、介護保険申請の原因となる病気などについて意見書を書いてもらいます。
その主治医意見書と認定調査を基に、コンピューターが介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)を算出しレベル分けされます。
STEP3 要介護認定の審査
次に保健・医療・福祉の学識経験者により構成された介護認定審査会により、一次判
定結果、主治医意見書に基づいて審査判定を行い審査されます。
STEP4 要介護認定
介護認定審査会の結果に基づき、市町村が申請者についての要介護認定を行い、以下いずれかの区分によって通知が届きます。
・非該当(自立)
・要支援 (1・2)
・要介護(1〜5)
2.認定結果に応じたサービス内容

要支援状態
「要支援1」「要支援2」:介護保険の介護予防サービスを利用することができます。
要介護状態には該当しませんが、身体上又は精神上の障害があってIADL(手段的日常生活動作)において何かしらの支援が必要な状態(虚弱状態)のことです。
| 要支援1 | IADL(手段的日常生活動作)においてなんらかの支援が必要な状態。 基本的な日常生活は送れる能力はあるが、歩行や立ち上がりなどに若干の低下が認められ、一部介助が必要。 |
|---|---|
| 要支援2 | 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力IADL(手段的日常生活動作)がわずかに低下し何らかの支援が必要。 |
※手段的日常生活動作=IADL(Instrumental Activities of Daily Living)
買い物、家事全般、服薬管理、支払い手続き、趣味の活動など、日常生活を送る上で必要であると言われている動作。
要介護状態
「要介護1~5」に認定:介護保険の介護サービス(在宅・施設)を利用することができます。
身体上の理由で寝たきり、または認知症などの精神上の障害があって、入浴、排泄、食事などの基本的なADL(日常生活活動作)においての全て、または一部について常時介護を要する状態のことです。
| 要介護1 | 立ち上がり、歩行に支えが必要で、排せつ・入浴・洗顔・衣服の着脱など部分的な介助が必要。 |
|---|---|
| 要介護2 | 立ち上がり、歩行に支えが必要で、排せつ・入浴・洗顔・衣服の着脱などに一部または全介助が必要。 |
| 要介護3 | 日常生活動作が著しく低下し、自分で立ち上がりや排せつができない。 排せつ・入浴・洗顔・つめ切り・衣服の着脱などに全介助が必要。 |
| 要介護4 | 自分で立ち上がりや歩行ができなく、排せつ・入浴・洗顔・衣服の着脱などの全般について全面的な介助が必要。 認識力・理解力などに衰えもある。 |
| 要介護5 | 生活全般にわたって全面的な介助が必要。 多くの問題行動や全般的な理解力も低下している。 |
※日常生活動作=ADL(Activities of Daily Living)
食事や排泄、整容、更衣、入浴、移乗、歩行など、私たちが日常生活の中でごく当たり前に行っている身体動作のことを言います。
つづいて、審査結果に不服がある場合についての解説です。
■次のページでご紹介します。
- 1
- 2
