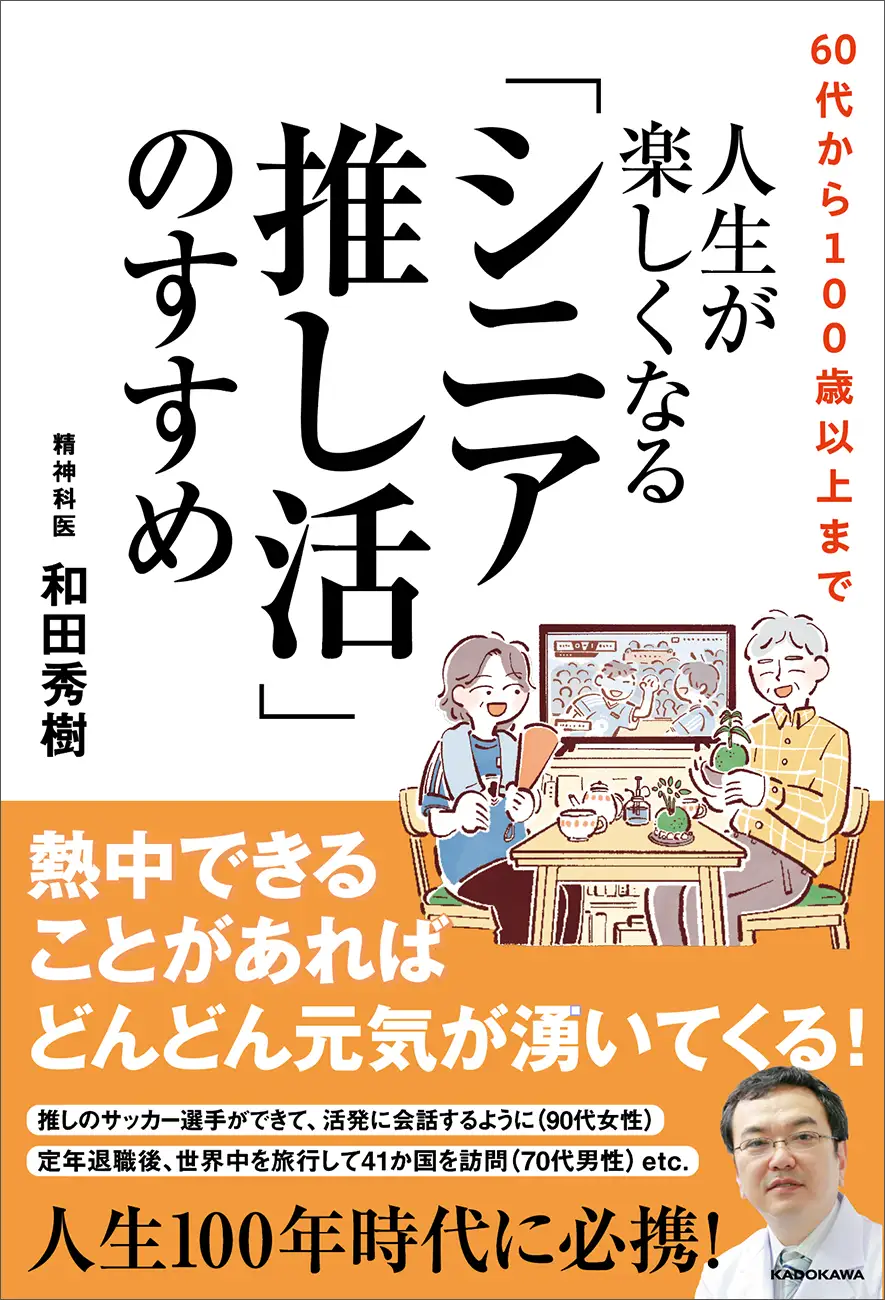家族の介護を続けていると、先が見えずに気持ちが疲れてしまうこともありますよね。介護する側の心と体に負担がかかる「介護ストレス」は、誰にでも起こりうるものです。
この記事では、介護ストレスが現れたときに出やすい身体・精神のサインや、介護保険サービスを活用して負担を軽くする方法を紹介します。
1. 介護で疲れるのはなぜ?主な原因と現れるサイン
介護で一番つらいのは、その「終わり」が見えにくいことです。
またストレスは自分でも気づきにくく、「最近少し疲れているな」と感じた時点で、早めに対処法を考えることが大切です。
いくら大切な親の介護とはいえ、在宅介護ではスペースや相談相手が限られるため、どうしても閉鎖的になりやすい傾向があります。
介護ストレスが現れるサイン
筆者が介護士として働いていたときも、「介護の方法がわからない」「親が本当に快適に過ごせているのか不安」という葛藤を抱えた方が、心身の限界を感じて施設入居を決めるケースが多くありました。
体や心に不調を感じながら無理を続けると、いわゆる“介護うつ”になることもあり、最悪の場合は共倒れにつながるおそれもあります。
介護される側の健康チェックと同じように、介護する側の心身にも以下のようなサインが出ていないか確認してみましょう。
精神的な負担
孤独を感じたり、将来に明るいイメージを持てなくなるのはつらいものです。頭では理解しているのに親にイライラして声を荒げてしまう、1人になると涙が出てしまう──そんな状態が続くようなら、介護ストレスが強まっているサインです。
身体的な負担
介護は、小さな赤ちゃんのお世話とは違い、体を支えたり持ち上げたりする動作が多いため、介護する側の身体への負担も大きくなります。
腰や膝を痛めるのはもちろん、自分の持病の治療を後回しにしてしまうケースも少なくありません。筆者自身も、そうした無理が重なって体調を崩された方を何度も見てきました。
2. 介護の負担を軽くするための5つのヒント

介護を続けるうえで大切なのは、ひとりで抱え込まないこと。ここでは、介護負担を少しでも軽くするための5つの工夫をご紹介します。
①介護保険サービスを上手に使う
介護の負担を感じ始めたら、我慢せずに介護保険サービスを積極的に活用しましょう。
すでに要介護・要支援の認定を受けていれば、在宅介護を支えるさまざまなサービスを利用できます。
■親の介護が必要になった時にするべき5つのこと
デイサービスや訪問介護、リハビリ施設を利用すれば、親を安心して預ける時間ができ、自分自身の休息やリフレッシュにもつながります。
また、介護用品のレンタルや住宅改修の費用補助などもあり、介護費用の自己負担を抑えながら、親の身体機能維持や生活の質の向上にも役立ちます。
介護保険サービスの利用計画(ケアプラン)は、担当のケアマネジャーが家庭の状況に合わせて調整してくれるので安心です。
「もっと楽に介護できる方法がないかな」と感じたときは、まずケアマネジャーに相談してみましょう。
介護する人が無理をせず、自分の時間を保ちながら続けられる環境を整えることが、長く介護を続けるための第一歩です。
②在宅介護に役立つ福祉用具を活用する
介護ベッドを使えば、介助する人の腰への負担を軽減できます。また、歩行器などの福祉用具をレンタルすることで、自力歩行が可能になるケースも多く、介助の回数を減らすことができます。
必要な用具をそろえるだけでも、毎日の介護がずっと楽になります。
③こまめに気分転換をする
介護のために自分を後回しにしてしまうと、心が疲弊し、介護うつにつながることがあります。
たとえ短い時間でも、買い物や散歩、趣味など「自分の好きなこと」をする時間を意識的に取りましょう。
介護する人の心を守ることは、結果的に介護される人の安心にもつながります。
無理をせず、自分を大切にする時間をぜひ確保してください。
④自分を責めない
介護には「これが正解」という形がありません。
「もっとこうしてあげればよかった」と悩む方も多いですが、そのときの自分にできる精一杯のことをしていれば、それはきっと伝わっています。
自分を責めすぎず、心を休める時間を持ちましょう。
介護の負担が増えると、仕事を辞めざるを得ないケースも少なくありません。介護と仕事、どちらも大切だからこそ、ひとりで抱え込まないでください。
そんな“介護離職”を防ぐために、いま国がどんな支援を用意しているかご存じですか?介護離職を防ぐための制度や支援策を、わかりやすくまとめた記事はこちらからどうぞ。
■介護離職を防ぐための支援制度|ワーキングケアラー必見の最新対策
⑤施設への入居を検討する
介護の負担が重くなってきたとき、施設への入居を考えることは悪いことではありません。
ただし、地方自治体や社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上でなければ入居できず、待機者も多いのが現状です。
民間の有料老人ホームは入居費用が高額になる一方で、まだ身体機能がしっかりしている方には窮屈に感じることもあります。
そこでおすすめなのが「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」です。
サ高住は生活の自由度が高く、一般の賃貸と同じ「賃貸借契約」で入居できるため、比較的入りやすく安心して暮らせる点が魅力です。
介護付き施設まではまだ早いけれど、見守りや生活支援が受けられる住まいを探している方に向いています。
→ サービス付き高齢者向け住宅を探す
 積水ハウス「グランドマスト」は、日々の生活をサポートするコンシェルジュ常駐、食堂完備、高齢者の方が安心・快適に暮らすためのサービスを備えた賃貸住宅です。
積水ハウス「グランドマスト」は、日々の生活をサポートするコンシェルジュ常駐、食堂完備、高齢者の方が安心・快適に暮らすためのサービスを備えた賃貸住宅です。■「グランドマストシリーズ」その魅力とは?
■「グランドマスト・シリーズ」物件一覧2021年9月24日
3. 介護と上手に距離をとる時間も大切に
多くの人が、いずれ年を重ねて親の介護に向き合う時期が訪れます。元気だった親が弱っていく姿を見るのはつらく、現実を受け入れられない気持ちになることもあるでしょう。
また、介護する親の姿を“未来の自分”に重ねてしまい、気持ちが沈んでしまう方も少なくありません。
しかし、介護は長い時間をともに歩む“長期戦”です。介護を続けるためには、ご自身の心と体を上手に守ることが何より大切です。自分大切にできる人こそ、相手を思いやる余裕を持てるものです。
もし「疲れたな」と感じたら、1人で抱え込まずに、信頼できる人や専門機関に早めに相談してみてください。ちょっとした休息や気分転換が、再び笑顔で介護に向き合う力を取り戻すきっかけになります。
幼少期から介護士に憧れる。10代で早めに出産を終え、介護士として有料老人ホームを軸に幅広い経験を積む。「もっと多くのシニアの幸せをお手伝いしたい」という思いを持ち、介護士をしていたからこそ分かる介護やシニアの実際の生活にコミットしたコラムを発信している。
親の介護 関連記事
■遠距離介護の親をどう支援すべきか? 事前の準備が大切
■一人暮らしをする老親が心配!でも同居が難しい場合どうする?
■都会で増える親の呼び寄せ問題|同居か?近居か?それぞれの事情と成功のポイント
■【体験談】同居に失敗!親の呼び寄せは近居のほうがうまくいく場合も
■親の突然の入院であわてないために|相談先・退院後の暮らしの選択肢
■【在宅介護か?施設介護か?】あなたはどちらを選択しますか

【広すぎる・老朽化した戸建てを賃貸で貸す「住み替え運用」】自宅を売却しないで賃貸にすることで安定した収入を得ることができます。その家賃収入で安心快適な賃貸住宅への入居も可能に。詳しい記事はこちら2021年9月21日