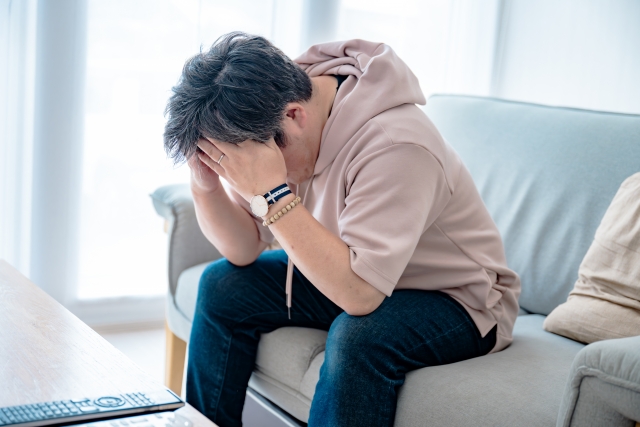「うちの親に限って、そんなことは…」
そう思っていたご家族が、ある日突然、警察からの電話を受け取る──それが「認知症による徘徊」の現実です。
前編では、実際の保護体験と、なぜ徘徊が起きるのか──その背景をお伝えしました☟
■【前編】認知症による徘徊はある日突然に──親を守るため体験談から学ぶポイント
今回の【後編】では、「万が一の前提」でできる5つの備えを解説します。
徘徊は完全には防げなくても、早期発見と命の安全につながる工夫はたくさんあります。「まだ大丈夫」ではなく、「今からできること」を一つずつ始めていきましょう。
1.認知症の徘徊は防げない?家族ができる「5つの備え」具体策
徘徊は、完全に防ぐことが難しいものの、事前に備えておくことで、万一のときの早期発見や安全確保につながります。
「何かあってから」では遅いため、日常生活の中で無理なくできることから対策を始めていきましょう。
ここでは、家族が今すぐ取り入れられる5つの備えをご紹介します。
まずは一番大切な、「万一発見されたとき、すぐに身元がわかる工夫」から見ていきましょう。
①名前や連絡先を常に身につけさせる
バッグやポケットに「名前・住所・連絡先」を記載したメモを入れるだけでも、発見時に大きな助けになります。
外から見える名札やIDカードを首から下げると、第三者にも気づいてもらいやすくなります。
- 衣類のタグや肌着にネームテープを貼る
- 防水ホルダーや布に印字できるスタンプも便利
- 文字は大きく、見えやすい場所(首元・手首・靴)に設置を
②GPS端末を活用する
靴のかかとに入れるタイプや、ベルト・カバンに付けられる小型GPSなど、装着しやすい端末が増えています。
スマホと連携させれば、現在地をリアルタイムで確認可能です。
- 移動履歴が確認できる機能
- 一定範囲を出たら通知が届く設定
- 電池の持ち時間と充電のしやすさ
- 自治体によっては助成金の対象となることも
- ※サンダル派の方には、衣類やカバンに装着できるタイプが安心です
③自治体の「見守り登録制度」に登録する
多くの自治体では、あらかじめ認知症の方の情報を登録しておくことで、万一の保護を迅速に行える制度があります。
QRコード付きのシールやキーホルダーを身につけることで、発見時にすぐ連絡をもらえる仕組みです。
- 登録には顔写真や身体的特徴の情報が必要な場合あり
- 洋服・靴・杖など、日常的に使う物にタグを付ける
- 制度名や窓口は自治体ごとに異なるので、「認知症 SOSネットワーク+市区町村名」で検索を
④外出先での“突然の徘徊”にも注意する
「徘徊」は自宅から出ていくだけでなく、外出先で突然起こるケースも多いです。
実際によくある例
- 病院の待合室で立ち上がり、そのまま外へ
- スーパーで目を離した隙に消えてしまう
- トイレに行くと言って姿を消す
備えのポイント
- トイレの前で待つ、車に一人で乗せないなど家族で役割分担
- 出入り口が管理されている施設を選ぶ
- 事前に店や病院と「万一の対応」について相談しておく
⑤「うちの親に限って」は通用しない
認知症の進行は、ある日を境に急変することがあります。「今日はたまたま落ち着いていただけ」という可能性もあるため、油断せず備える姿勢が重要です。
気づきのヒント
- 「まだ大丈夫」は、実はもっとも危ういサインかも
- 相手の尊厳を守りながら「守る準備」を自然に取り入れる
- 家族で情報を共有し、小さな工夫から始めましょう
2.日頃の備えが命を守る
家族に認知症の方がいると、日々の生活には大きな負担や緊張が伴います。
「いつ外に出てしまうかわからない」「夜も気が抜けない」――そんな不安と向き合いながら、毎日を過ごしている方も多いでしょう。
外に出てしまったとき、つい心配のあまり叱ってしまい、「なんであんな言い方をしたんだろう…」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
でも、それは大切な人を思う気持ちがあるからこそ。だからこそ、家族だけで抱え込まないこと”が大切です。
地域包括支援センターやかかりつけ医など、信頼できる窓口に早めに相談することや、GPSや見守りタグといった支援制度を利用することも、家族の負担を減らす大きな助けになります。
まずは、できることから一つずつ。あなたとご家族に合った方法を、無理のない形で取り入れていきましょう。
徘徊は、本人にとっては“意味のある外出”であっても、命の危険につながる行動でもあります。
けれど、日頃の備えや地域との連携によって、早期発見や無事の保護につながる可能性は確実に高まります。
そして、道で「もしかして…?」と思う高齢者を見かけたときには、どうか迷わず声をかけてください。
あなたのその行動が、誰かの命を守る第一歩になるかもしれません。
3.認知症や徘徊に関する相談先
備えを進めるうえで、困ったときに相談できる窓口を知っておくことも大切です。身近な公的機関を上手に活用しましょう。
- 地域包括支援センター
各市区町村に設置されている高齢者支援の総合窓口です。認知症に関する相談や、地域で利用できる制度・サービスについての情報提供を行っています。 - 認知症の人と家族の会(公益社団法人)
介護者からの相談に応じる電話窓口があり、全国に支部を持つ団体です。家族交流会や情報提供も行っています。 - かかりつけ医・もの忘れ外来
日常的な変化に気づいた際は、医療機関で早めに相談を。認知症サポート医や専門医が対応してくれる医療機関もあります。 - 自治体の高齢福祉課・認知症支援窓口
GPS端末の助成や、見守りシール・登録制度についての案内など、地域によって独自の支援策がある場合があります。
あわせて読みたい|前編はこちら☟
徘徊はある日突然に──認知症の親を守るため体験談から学ぶポイント
(グッドライフシニア編集部 松尾)
参考:厚生労働省:「行方不明を防ぐ・見つける 市区町村・地域の取組事例」
公益社団法人 認知症の人と家族の会:「緊急要望書」
■要介護1で一人暮らしは続けられるか?認知症の場合はどうする
■認知症の介護がつらい…認知症介護のお悩みトップ3の対処方法とは?
■見逃さないことが大切!認知症の主な兆候とは
■性格が関係する!? 認知症になりやすい人、なりにくい人
■認知症の人は嘘をつく!? その嘘には深いヒミツがあった
■自宅でもできる!認知症リハビリテーションのすすめ