
親が近くに住んでいるならよいですが、遠方で一人暮らしをしている場合、いざという時にすぐに駆けつけることができません。
「そろそろ近居や同居を考えなければ…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回は、老親(ろうしん)の一人暮らしが抱える問題点と、同居が難しい場合の対応策などについて考えてみましょう。
1.一人暮らしをする高齢者は年々増加
自分の親には、いつまでも元気でいて欲しい。子としては、そう願うものですが、現実には年を重ねるにつれ体力・気力が衰え、子どもや周りのサポートが必要になる機会も増えてきます。
また、諸事情により一人暮らしをされている高齢者の方も多くいらっしゃいます。
内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によると、65歳以上の一人暮らしの割合は2020年時点で男性15.0%、女性22.1%。1980年と比べると男女ともに3倍以上に増加しており、今後も上昇が見込まれています。
今は一人暮らしでない方も、子どもの独立や配偶者との離別・死別などによって誰もが当事者となりうる身近な問題です。
2.高齢者の独居が抱える不安はどのようなもの?
高齢者の一人暮らしには、どんな問題点があるのでしょうか。新婚1年目のA子さん。彼女の義父に起きた実際の体験談をご紹介します。
原因がわからないまましばらく自宅安静となりましたが、数週間は起き上がることもままならず、介護のために自宅に通うことになりました。

その後少しずつ回復し、今では職場復帰もできましたが、自宅に一人でいるときに義父にまた同じことが起こったらと思うと、心配で仕方ありません。
頻繁に様子を見に行ければ一番良いのですが、仕事や家庭のことを考えると難しく、もどかしい気持ちです。
A子さんの事例からもわかるように、まず考えられる問題点は「一人の時に助けを呼べない」ということです。
外出先であれば、体調が悪くなっても代わりに対応してくれる人がいます。しかし、家に一人でいるときに意識を失うなどの非常事態が起きた場合、誰も助けることができません。発見が遅れれば、孤独死という最悪のケースも考えられます。
さらには、認知症を患っている方の一人暮らしには、本人やご家族も気づかないところで、日常生活にも様々な支障が出てくることがあります。
・生活習慣病(同じものを食べ続けるなど、食生活の乱れ)
・服薬管理ができない(持病の悪化、過剰摂取による副作用など)
・金銭管理ができない(高額商品の購入、詐欺被害など)
・ご近所トラブル(ゴミ出しができない、被害妄想など)
特に火の不始末や服薬トラブルは命にかかわる問題のため、早急に対応する必要があります。
ここで、常に様子を見守ることができる「同居」という選択肢が思い浮かびますが、実際にはできないというケースも多く見られます。
3.心配だけど…同居に踏み切れない
それでは、高齢の親との同居に踏み出せない理由には、どんなものがあるのでしょうか。
内閣府の発表によると、子どもと同居している65歳以上の高齢者の割合は、1980年には69%でしたが、2015年には39%にまで落ち込んでいます。
お互いのストレス
同居を始めると、テレビの音量・話し声・トイレといった生活音、食事の内容やタイミング、睡眠時間など、あらゆる面で気を遣うことになります。たまに会うのであればできる気遣いも、毎日となっては強いストレスに。
加えて介護も必要となれば、子どもが男子の場合、その配偶者の嫁にかかる負担はかなり大きなものとなります。
同居は、子どものお世話をお願いしたり、家事を分担したりと助かる部分もあるでしょう。しかし、それは逆に、子育てや家事のやり方に干渉されてしまうということでもあります。
そして親にとっても、子どもや孫のためにと頑張りすぎてしまい、肉体的・精神的に負担になっていることがあります。
こういったお互いの生活上の我慢や過干渉によるストレスを懸念して、同居を避けるケースが多いと思われます。
本人が同居を望まない
子どもやその配偶者が「親の呼び寄せ」を前向きに考えていたとしても、親本人が同居を望まない場合があります。
子供が都市部に住む場合、親が長年住み慣れた土地を離れたがらないケースが多いためです。持ち家の場合に家をどうするか? また、ご先祖様のお墓の問題、友人や親族と離れることなど、様々な心配事がでてくるため踏み切れないのです。
また、まだまだ元気で自立した高齢者の場合には、同居せずに自由に過ごしたいと考える方も多いでしょう。
関連記事
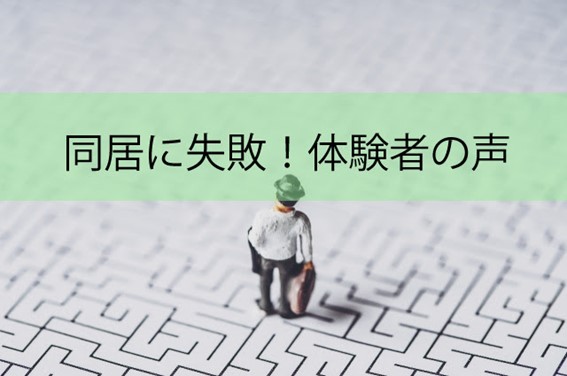 同居をしたもののうまくいかなかった方々は、どのようなことにストレスを感じ、同居を解消することになったのか?子世代の方に伺った体験談。
同居をしたもののうまくいかなかった方々は、どのようなことにストレスを感じ、同居を解消することになったのか?子世代の方に伺った体験談。■【体験談】同居に失敗!親の呼び寄せは近居のほうがうまくいく場合も
4.同居しないで近居を選択

遠方に住む親が一人暮らしを不安になっても、同居が難しい場合に近居を選択する方が多くいらっしゃいます。
子供の住む近くに、シニア向けに安心サポートが付いた賃貸住宅や老人ホームなどの施設があれば、親を呼び寄せて近居すれば、親も子もお互い近くにいるので安心です。
それでは、シニア向け賃貸住宅や有料老人ホームとはどんな施設なのでしょうか。
シニア向け賃貸住宅とは?
60歳以上の自立した方を対象にした住まいで、一般の賃貸マンションに“安心”の仕組みを加えた住宅です。見守り・緊急対応サービス、生活相談、バリアフリー設備などが整っており、日常生活をサポートする体制が備わっています。
施設ではなく「住まい」として自由度が高く、入居後も自分のペースで生活できる点が魅力です。見守りの目はほしいけれど、介護施設のような制約のない暮らしを続けたい──そんな方に最適の住まいです。
■シニア向け賃貸住宅とは?
また、将来に備えて「サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)」を検討する方も増えていますが、まだ元気で自立したシニアには、シニア向け賃貸住宅のほうが自由度が高くおすすめです。
■サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?
それぞれの特徴やサービスについてはこちらをご覧ください。
■「サ高住」と「高齢者向け賃貸」はここが違う!徹底比較
有料老人ホーム
有料老人ホームには、健康型(自立型)、住宅型、介護付き(専用型)の3つのタイプがあります。
健康型(自立型)
健康で自立した生活ができる高齢者が対象。介護が必要になった場合には施設内で介護を受けることができないため、転居する必要が出てきます。
住宅型
入居条件は自立~要介護まで施設によって異なり、ホーム自体には介護サービスが付いていません。在宅の人と同じように、必要に応じて介護保険を使ったサービス(訪問介護や通所介護など)を個別に利用するのが特徴です。
介護付き(専用型・混合型)
要介護1以上の高齢者だけが入居できるのは専用型。介護・看護職が配置されており、介護サービスを受けることができます。
要介護認定のない自立の方から入居できるのが混合型。入居後に介護度が上がっても、施設の介護サービスを受けながら生活を続けていくことができます。
■有料老人ホーム(介護付き・住宅型・健康型)とは?
費用やサービスの詳細は、施設によって異なります。わからないことはプロのアドバイザーに相談してみましょう。
同居をする場合も、近居をする場合も、それぞれのメリットやデメリットがあります。家族で十分話し合って親にも子にも双方にとってベストな選択を見つけてください。
最近では、見守りサービス付きの賃貸住宅や、子世帯の近くに住めるシニア向け住宅も増えています。こうした住まいを上手に活用することで、親も子も安心してそれぞれの生活を続けられます。
 【親の呼び寄せや近居に人気!】バリアフリー対応、緊急時の駆けつけ、訪問診療サービスなどで、高齢者が安心快適に暮らせるサービスの付いた賃貸住宅です。
【親の呼び寄せや近居に人気!】バリアフリー対応、緊急時の駆けつけ、訪問診療サービスなどで、高齢者が安心快適に暮らせるサービスの付いた賃貸住宅です。
⇒ 旭化成「ヘーベルVillage」、その魅力とは?
⇒ シニア向け賃貸を検索する
■都会で増える親の呼び寄せ問題|同居か?近居か?それぞれの事情と成功のポイント
■遠距離介護の親をどう支援すべきか? 事前の準備が大切
■離れて住む親の安否が心配!孤独死を防ぐ対策とは?
 筆者:熊戸まこ(くまど・まこ)
筆者:熊戸まこ(くまど・まこ)学習院大学法学部政治学科卒業。IT企業に3年間勤め、退職後はライターとして高齢者の介護や福祉、健康分野の記事を執筆しています。福祉分野の専門性を高めるため、現在は社会福祉士の国家試験を取得しています。

【入居者の声】子供との同居という選択ではなく、スープの冷めない近くに住む「近居」を選び、サ高住や高齢者向け賃貸に入居した方の生の声を集めました。
2020年3月18日
関連記事
■親家片(おやかた)とは?親の家を片付ける3つの方法で人生の整理整頓!
【体験談】親を呼び寄せるべきか?子どもが親の田舎に戻るべきか?
【体験談①通い介護に限界を感じ…】親にどう話した?老人ホーム入居をすすめるとき
【体験談②ひとり暮らしの母を呼び寄せ】施設や老人ホーム入居をすすめるときのポイント
【体験談③入院をきっかけに老健から老人ホームへ】親にどう話した?施設入居をすすめるとき



