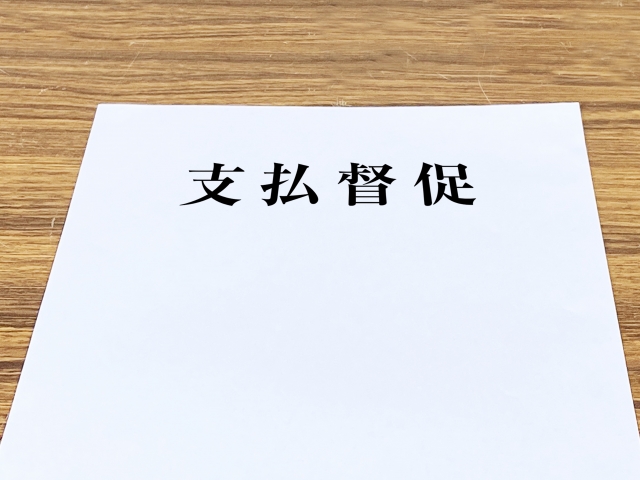
介護保険は40歳以上の人が支払う介護保険料によって、みんなが安心して介護を受けられる仕組みになっています。
以前は保険料の滞納者が増加していましたが、2024年の最新データでは滞納者数は減少傾向にあります。それでも、経済的な理由や制度への疑問から滞納する人は一定数おり、罰則を受けるケースも少なくありません。
また、支払える余裕があっても「特養になかなか入れない」「『介護』は自分には関係ない」など、制度への疑問や介護へのひとごと感から、保険料を支払うことへの意欲が薄れている人もいるとききます。
今回は、保険料を滞納することで発生するペナルティと保険料を納める意味を改めて考えたいと思います。
滞納による罰則は時効完成後もつづく
保険料を滞納した場合には、次のような滞納処分や給付制限が行われます。
滞納処分
保険料の納付期限から20日以降に、市区町村から督促状が送られてきます。督促手数料が100円程度、そして納付期限からの日数に応じた延滞金も加算されます。
電話や訪問による催告によっても支払われない場合には、預金や不動産などの財産の差し押さえ処分が行われることがあります。
非常に厳しい処分ですが、2019年度では全体の約4割にあたる642の市区町村が行っています。
給付制限
保険料を1年以上納めなかった場合、その期間に応じて給付制限が行われます。2年を過ぎると時効となってしまいますが、「時効が過ぎたから無罪放免」とはならないのがこわいところです。
介護保険料の滞納による罰則
| 滞納期間 | 影響 |
|---|---|
| 1年以上滞納 |
介護サービス利用時に「償還払い」へ変更。 例:通常1割負担(月1万円)の人でも、まず全額(10万円)を支払い、後日9万円を払い戻し申請する必要がある。 |
| 1年6か月以上滞納 |
保険給付の全部または一部が一時差し止められる。 差し止められた金額は、滞納している保険料に充当される。 |
| 2年以上滞納 |
保険料は時効で支払い不可に。 過去10年の滞納履歴をさかのぼり、自己負担が本来1割・2割の人でも3割負担に引き上げ(3割負担の人は4割負担に)。 また、高額介護サービス費の軽減制度の対象外となる。 |
保険料を1年以上滞納した場合
通常は、自己負担分だけを介護事業者に支払うことで介護サービスが受けられます。しかし1年以上滞納すると、自分でまず介護サービを払い戻してもらうという支払い方法に切り替えられます。
例えば、1割負担が適用されて月1万円の自己負担分を支払っている人が、1年以上保険料を滞納すると、いったん全額の10万円を支払います。9万円は、後日申請をして戻ってくるまで待たないといけません。
保険料を1年6か月以上滞納した場合
保険給付の全部または一部が一時差止められます。差止められた分は、滞納している保険料にあてられます。
保険料を2年以上滞納した場合
介護保険料は、滞納して2年が経つと、時効となって支払うことができなくなります。
実際に介護が必要になってサービスを利用するときには、時効によって滞納保険料を集めることができなくなった期間があるかを過去10年さかのぼって調査されます。
その期間に応じて、サービスを使うときの自己負担分が本来なら1割または2割ですむはずが、3割に引き上げられてしまいます(自己負担が3割の場合は4割へ引き上げ)。
また、高額介護サービス費などの利用者負担を軽減してくれる制度の対象からも外されてしまいます。
ほとんどの人は滞納の心配はないけれど
介護保険制度は、その財源の半分が公費(税金)で成り立っています。残り半分は、40歳以上の人が支払う保険料です。
保険料の納付方法は、65歳以上と65歳未満で異なります。
65歳以上の保険料の納付方法
| 年金額が年18万円以上 | 年金から天引きされる |
|---|---|
| 年金額が年18万円未満 | 市区町村から送られてくる納付書や口座振替で自分で納める |
40歳以上65歳未満の保険料の納付方法
| 健康保険などの場合 | 医療保険料とあわせて給与や賞与から天引きされる |
|---|---|
| 国民健康保険の場合 | 医療保険料とあわせて国民健康保険料として世帯主が納める |
このように、支払い義務のある人のほとんどは、年金や給与などからの天引きや医療保険料とあわせて、いわば強制的に保険料を支払っています。したがって、ペナルティを受ける心配はほぼありません。
その一方、注意が必要なのが、年金が少なく、自分で保険料を支払っている人です。うっかり忘れてしまった人や、低所得ゆえ、支払いが後回しになってずるずると滞納してしまうケースが多いようです。
介護保険料の上昇と支払い負担の現状
保険料の額は、住んでいる市区町村や加入している公的医療保険などで異なりますが、全国的に上昇傾向にあります。
介護保険制度が始まった2000年当時、65歳以上の全国平均保険料は2,911円でした。しかし、2018~2020年度では5,869円と、およそ2倍に増加しています。
この保険料を納められず、滞納によるペナルティを受ける人が依然として存在します。
また、支払える余裕があっても「特養になかなか入れない」「『介護』は自分には関係ない」など、制度への疑問や介護へのひとごと感から、保険料を支払うことへの意欲が薄れている人もいるとききます。
厚労省の発表によると、2019年度に介護保険料の滞納により財産を差し押さえられた65歳以上の人は1万9,221人にのぼり、過去最多を記録(厚労省「令和元年度介護保険事務調査」)。
しかし、2024年の最新データによると、滞納者数や滞納件数は減少傾向にあります。これは、自治体による早期の相談対応や減免制度の活用が広がったことが要因と考えられます。それでも、一定数の人が滞納しており、厳しい罰則を受けるケースは少なくありません。
65歳以上の世帯主の平均貯蓄額は1,213万円ですが、そのうち3,000万円以上の人が10.8%であるのに対して、貯蓄ゼロの人は14.3%となっています(厚労省「2019年国民生活基礎調査」)。
依然として経済格差が存在し、上がり続ける介護保険料への負担感が大きな課題となっています。
早めの相談で負担増を避けることが重要

介護保険料を滞納するといろいろな厳しいペナルティが待っていることが、おわかりいただけたと思います。
では、保険料を支払えない場合、打つ手はないのでしょうか。
まず、お住まいの市区町村によっては、失業や災害などの特別な理由があれば、保険料の支払い期限の延長や減免(減額や免除)を受けられる可能性があります。
最近では、このコロナ禍で支払いが難しくなった人のために、猶予や減免制度が設けられています。
また、世帯収入が少ない場合には申請すれば、所得段階に応じた保険料の減額を受けられる可能性もあります。
このように、行政も支払いが苦しい人たちに対して、ただ手をこまねいているだけではありません。
保険料を支払うことが難しくなってきた人は、早めに市区町村の窓口に相談しましょう。
延滞金などの保険料以外の支払いが増えることを防ぎ、受けられるはずだった介護を受けられなくなることを避けて、「将来の自分や家族」を守ることが重要です。
まとめ
「元気なうちから、『介護』に対してもっと当事者意識をもってほしい」
介護の必要になった高齢者やその家族に日夜向き合う介護関係者や地域の行政関係者に話をきくと、必ずと言っていいほど耳にする言葉です。
介護を必要とする平均的な期間は、8~12年といわれています。そんな人生において大変な時期をささえるのが介護保険です。
介護保険制度の存続、そしてより良い制度づくりを支えているのは、私たちが支払う保険料。普段はあまり意識する機会はないかもしれませんが、滞納の課題をはじめとする制度の行方をしっかり見守る姿勢が求められます。
会社勤務を経て、高齢者分野を中心に活動するフリーライター。「高齢者ご本人やそのご家族、そして介護職が、自分の人生を大切にできる社会」について考え中。保有資格は社会福祉士。



