
家が健康に与える影響が注目されるも、依然として低い関心度
高齢者にとって「寒い家」は、健康を脅かす重大なリスクです。
冬の室内の寒さは、血圧の上昇やヒートショックを引き起こし、命に関わる危険性さえあります。しかし、体調不良を「年のせい」「仕方ない」と見過ごしてしまうケースも少なくありません。
特に、昭和55年(1980年)以前に建てられた住宅は断熱性能が低く、現在の基準を満たしていない住宅も多く、冬の室内温度が大きく下がりやすい傾向があります。日本の高齢者世帯の約7割がこうした持ち家に住んでおり、寒さによる健康リスクを抱えやすい環境にあるといえます。
国や医療機関も「住まいの温度が健康に直結する」と警鐘を鳴らしていますが、内閣府の調査では「健康を重視したい」と答える人が8割を超える一方で、「住まいの環境改善」を優先する人はわずか約1割にとどまっています。
つまり、多くの人が健康を意識していても、住まいの寒さを“健康問題”として捉えていないのが現状です。この意識のギャップこそが、冬の健康被害を招く大きな背景といえるでしょう。
寒い家が高齢者にもたらす健康被害とは?
海外の公衆衛生機関では、室温が18℃を下回ると、循環器系や呼吸器系の疾患、低体温症などの健康リスクが高まると警告しています。
WHO(世界保健機関)も、「冬季は18℃以上を確保することが、寒さによる健康被害を防ぐ安全な室温」と提言しています。
日本でも、冬の住宅環境が健康に与える影響は深刻で、特に高齢者にとっては命に関わることも少なくありません。寒い家に住み続けることで、血圧の上昇やヒートショック、低体温症、関節痛、脱水など、さまざまな症状が引き起こされる可能性があります。
以下では、寒い住環境がもたらす代表的な健康被害と、それぞれの対策を詳しく紹介した記事をまとめました。気になる症状がある方は、ぜひ各記事をチェックして、今日からできる予防のヒントを見つけてください。
高血圧
国内でも国交省発案による調査から、床付近の室温が低い家=足元が寒い家では、高血圧の通院リスクがそうでない家と比較して1.53倍であることが確認されています。
窓や扉の断熱性、住宅内での過度な温度差、暖冷房の効果的な配置など改修工事や工夫に取り組んだ家では、住人の最高血圧値が低下し、住宅内の安定した温度保持が高血圧予防につながる例も報告されています。
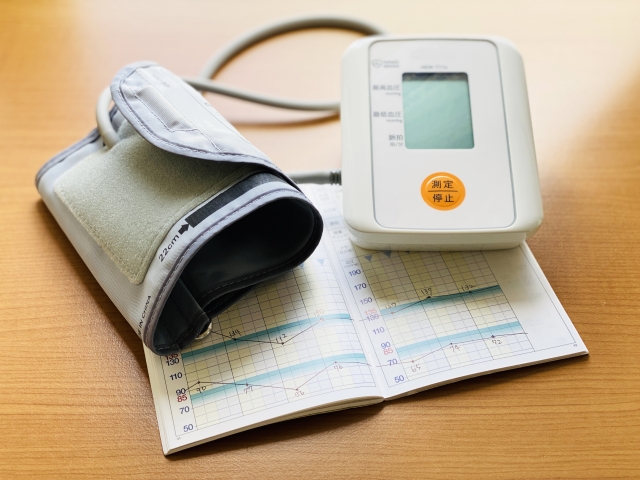 放っておくと危ない!高齢者の高血圧(その症状や対策)
放っておくと危ない!高齢者の高血圧(その症状や対策) 高血圧は、脳血管や心臓の病気につながる危険性がある、決して甘く見てはいけない生活習慣病。この記事では、特に高齢者の方に気を付けてほしいポイントをご紹介します。
低体温症
低体温症とは、直腸の温度(直腸温)が35℃以下になった状態のことを言います。
高齢者の低体温症患者が救急搬送されるケースも多くあり、冬で外の気温が低いことで低体温症が起こると思われがちですが、室内でも起こりえます。
認知症や普段あまり話をしない高齢者の場合、症状が分かりにくいため、気がついたときには重症化しているケースもあります。
関節痛(膝・腰・肩の痛み)
関節に慢性の痛みがある方は、冷やさないようにしなければいけません。
関節周囲には、軟骨や脂肪、筋肉などの軟部組織が集まり、痛みがある人の軟部組織は炎症を起こしています。
この炎症があると発痛物質が集まり、患部が冷えると血行が悪くなり痛みが増してしまいます。
ヒートショック(心筋梗塞や脳卒中の引き金にも)
冬の入浴や夜のトイレは高齢者の場合、ヒートショックを起こしやすいため特に注意が必要です。全国で起こった入浴中の急死数は年間約19,000人にも上ります。
ヒートショックとは、温かいリビングなどから、寒い脱衣所やトイレに移動したとき、急な温度変化で血圧が上下することで体に与えるショックのこと。心臓に負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中の引き金になりやすいのです。
かくれ脱水
かくれ脱水とは、本人も自覚がないうちに体内の水分が奪われ、脱水症の一歩手前になっている状態のことです。
夏場は脱水に気をつけますが、高齢者の場合は冬場に脱水を起こすことがあるので注意してください。
暖房を使用するため空気も乾燥し、汗をかいていないのに体から水分が失われているという状態になりやすいためです。
 「かくれ脱水」にご注意!予防と水分補給のポイントとは?
「かくれ脱水」にご注意!予防と水分補給のポイントとは?脱水症を未然に防ぐには水分補給が大切。脱水がどのような状態で起こるのかを知り、かからないためにも日ごろから予防を心がけましょう。脱水チェックリスト付き。
寒さ対策は“あとで”ではなく“今すぐ”に
寒い家をそのままにしておくと、知らないうちに体への負担が積み重なっていきます。特に高齢者にとっては、わずかな温度差が血圧の急変やヒートショックなどの健康リスクにつながることもあります。
人は年齢を重ねると、若いころよりも体温調節機能が低下し、寒さを感じにくくなります。そのため「まだ大丈夫」と感じていても、体はすでに冷えによるストレスを受けていることがあります。「寒い」と感じる前に、家の断熱性や日々の防寒対策を見直すことが大切です。
少しの工夫や住まいの見直しで、冬の暮らしは驚くほど快適になります。日々の快適さと健康を守るためにも、「暖かく過ごす工夫」をこの冬から取り入れてみましょう。
こちらの記事では、大掛かりなリフォームなど不要!すぐに実践できる簡単な防寒対策をご紹介します。室内を温かく保つアイディアを実践してみましょう!
■冬の室内を暖かく!寒い家の中で快適に過ごすためのアイデア7選
冬の寒さや室内の温度差による健康リスクを軽減するには、住宅の断熱・気密性能が大きなカギになります。壁や窓の断熱性を高めることで、室内の温度を一定に保ちやすくなり、ヒートショックのリスクを大幅に減らせます。
もし、現在の住まいで寒さ対策が難しい場合は、もともと断熱性に優れた賃貸住宅へ住み替えるという選択肢もあります。
たとえば旭化成ホームズの「ヘーベルVillage」は、鉄骨ALC構造による高い断熱性と気密性を備えた住まい。外気の影響を受けにくく、室内の暖かさを長時間キープできるため、浴室やトイレ、居室の温度差を最小限に抑えられます。これにより、ヒートショックや冷えによる不調を防ぎ、冬でも快適に過ごせる環境が整っています。
▶ 旭化成のシニア向け賃貸住宅「ヘーベルVillage」その魅力とは?
▶ 高気密・高断熱仕様のヘーベルVillage物件をチェックする
※空室状況は変動するため、個別ページへの直リンクではなく検索TOPへご案内します。
参考:東京ガ都市生活研究所都市生活レポート『寒い住宅の健康リスクを知ろう!高齢者が安心して住める家』
(グッドライフシニア編集部 松尾)






