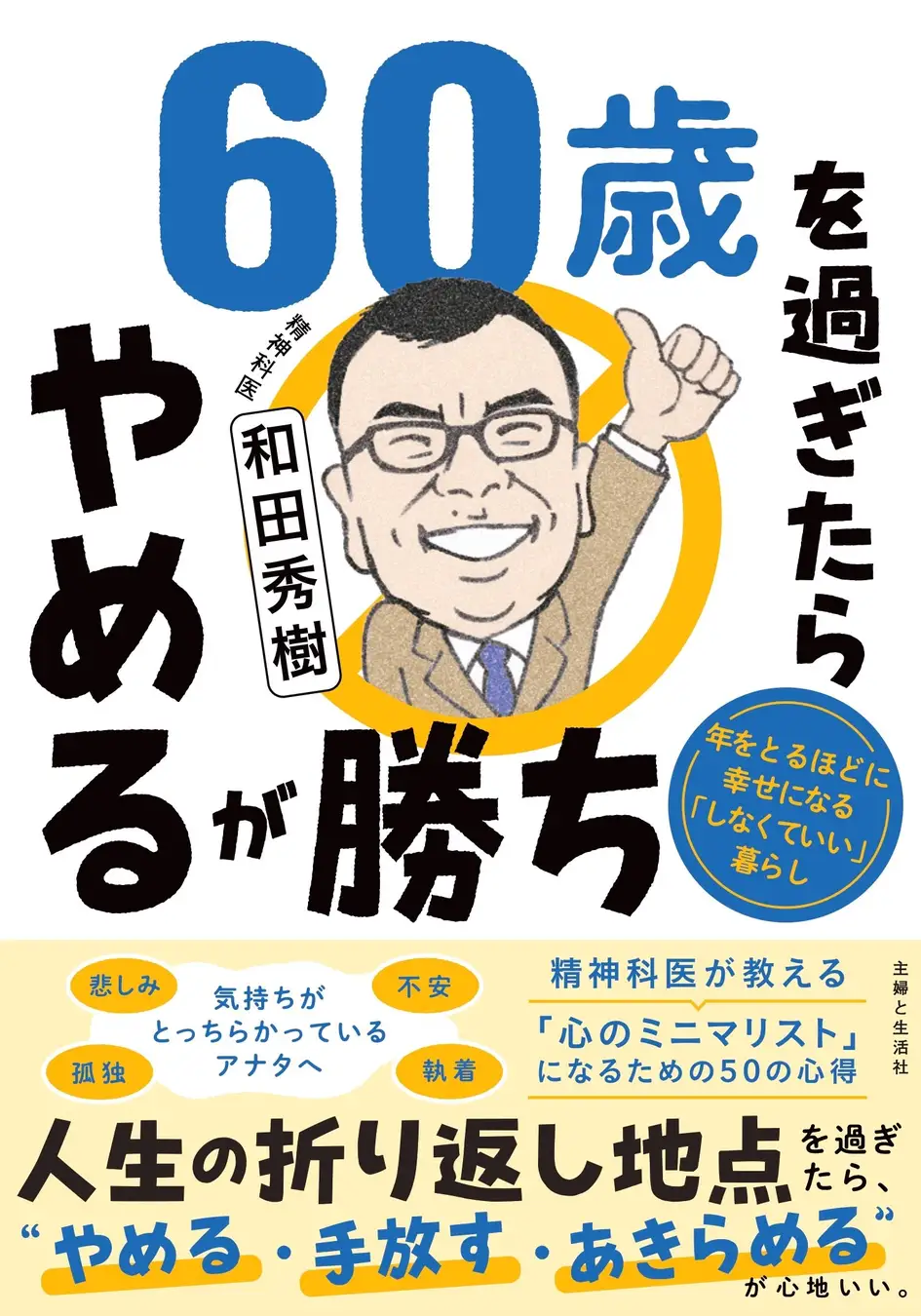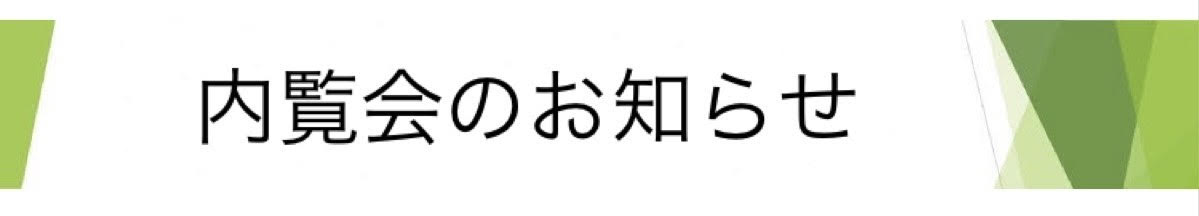遠距離介護は、親も子も住み慣れた環境を維持できる反面、時間や費用の負担も大きくなりがち。「このまま続けられるだろうか」「親が急に体調を崩したらどうしよう」と不安を感じる方も多いでしょう。
この記事では、遠距離介護のメリット・デメリットを整理し、長く続けるための工夫や、無理を減らすためのサポート活用法をわかりやすく紹介します。
知っておきたい遠距離介護のメリット・デメリット
総務省の調査によると、親と子が別々に暮らしている高齢者世帯は約7割にのぼります。仕事や子育てを続けながらの遠距離介護は、今や多くの家庭が直面している課題です。
まずは、メリット・デメリットについて掘り下げてみましょう。
遠距離介護のメリット
親、子の両方が、転居せずにこれまでの生活を継続することが可能です。
親の“生きがい”を守りやすい
長年の友人関係や地域活動など、親の生活基盤を維持できることは、精神的な安定につながります。介護を理由に環境を変えると、意欲の低下や認知機能の低下を招くケースも。
高齢者にとっては、環境の変化に適応するのが難しい場合も多く、住み慣れた地域で暮らし続けられることは、結果的に健康維持にもつながるのです。
子も仕事や家庭を維持できる
子世代にとっても、通勤や家庭のペースを大きく崩さずに介護を続けられる点は大きなメリット。インターネットが普及した今は、オンラインでの会話や見守りツールを併用すれば、離れていても支援の質を保つことができます。
住み慣れた場所を離れることなく介護が実現するためお互いが自分の時間を維持でき、365日一緒にいるわけではないので精神的ストレスを最小限に抑えることが可能な介護パターンといえるでしょう。
また、親の介護度が進み施設介護を望むことになった場合、在宅介護者に比べて優先的に施設への入所が可能となります(親が独居の場合は特に)。
遠距離介護のデメリット

親の変化に気づきにくい
週末にしか会えない場合、体調や認知の変化を見逃してしまうことがあります。「この前は元気そうだったのに…」というケースも少なくありません。
地域包括支援センターや訪問看護など、第三者の定期的な目を入れることが安心につながります。
兄弟間の温度差が生まれやすい
離れて暮らす家族間で「誰がどこまで関わるか」の意識差が生じやすいのも遠距離介護の難点です。早めに「連絡頻度」「費用の分担」「緊急時の判断基準」を家族で話し合っておくことが大切です。
経済的・身体的負担
経済的・身体的な負担が大きくなりやすい点にも注意が必要。子が親の元に通うための交通費がかかります。その距離が遠いほど、また回数が増えるほど、支出、および身体的な負担が増えます。
また、介護のために勤務先の仕事を減らした場合、収入減となることもあります。
さらに、子が介護できない日々の介護については介護保険サービスを利用することになるため、その分費用がかかるでしょう。
遠距離介護以外については、以下の記事が参考になります。
■在宅介護か?施設介護か?|それぞれのメリットとデメリット
遠距離介護を持続させるコツ
「介護」は精神的、そして身体的な負担が大きくなりやすく、最悪の場合うつ病を発症するケースもあります。
親への心配がつのり、通う日数を増やすと介護者の負担が大きくなることも…。そうならないためには、人の力を借りることが大切です。
担当ケアマネージャー、介護士などの専門家に積極的に相談し、介護保険サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護など)を最大限に活用することで、通う日数を調整しましょう。
1. 介護サービスの“曜日割り”を決める
訪問看護・訪問介護・デイサービスなどを曜日で分け、「どの日にどの支援が入るか」をスケジュール表にまとめておきましょう。カレンダーを家族間で共有しておくと、緊急時も連携しやすくなります。
2. 緊急時対応を事前に整える
救急搬送先・主治医・キーパーソン連絡先などを記した「緊急時連絡シート」を作成し、冷蔵庫などすぐ見える場所に貼っておくと安心です。地元の民生委員やご近所の信頼できる方にも、連絡先だけでも伝えておくといざというときに助けてもらえます。
3. テクノロジーを味方につける
遠距離介護で頼りになるのが、スマート家電や見守りセンサー。電気・ドアの開閉・冷蔵庫の稼働状況を感知して異常を通知するタイプや、スマホアプリで室温や生活リズムを確認できるものもあります。
遠隔操作によって要介護者の様子をスマホやパソコンから見守るサービスも安価で提供されているので、誰もいない時間帯はこのようなツールを活用するのもおすすめ。
親子で「監視ではなく安心のため」と話し合って導入するのがポイントです。
その他、近所の人に日ごろから状況を説明し、いざというときには様子を見てもらえるようお願いしておくと心理的負担も減るでしょう。
遠距離介護を続けるために、次の一歩を考える
遠距離介護は費用がかさむデメリットがあるものの、親と子が自分の生活を大切にしながら支え合える、前向きな介護の形でもあります。
離れているときの介護体制、誰もいないときの見守り手段、体調不良時の受け入れ病院や介護サービス事業所を事前に把握しておくと安心です。
そして何より大切なのは、「物理的な距離」だけでなく「心の距離」を近づけること。
家族や地域、専門職など、人と仕組みの力を上手に借りながら、無理のない形で支えることが、遠距離介護を長く続けるためのいちばんのポイントです。
あわせて読みたい記事
遠距離介護の親をどう支援すべきか? 事前の準備が大切です
もし「今のままでは負担が大きい」と感じたら、住まいの形を見直すのも一つの方法です。
「できるだけ自宅で過ごしてほしいけれど、距離があると不安…」という方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、見守りと支援がある住まいを検討してみるのも一つの方法です。サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)なら、介護が必要になる前から安心して暮らせる環境が整っています。
サ高住とは、簡単に言えば、食事サポートが受けられる、安心なサービスが整った高齢者向け賃貸住宅のことです。詳しくはこちらの記事もご覧ください。
■サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?
東京や神奈川など首都圏では、「親世帯を呼び寄せて近居する」スタイルでサ高住を選ぶ方が増えています。
→ 安心して暮らせるサ高住を探す
最新のサ高住やシニア向け賃貸の空室状況は、姉妹サイト「シニア賃貸60+」で確認できます。
→ シニア賃貸60+で空室を探す
(グッドライフシニア編集部 松尾まみ)
■介護保険制度とは?その仕組みを詳しく解説
■介護保険料を滞納するとどうなる?どんな罰則が待ち受けるかを解説
■介護認定調査を受けるに当たり知っておくべきこと ~親の自尊心も大切に~
■「サ高住」と「有料老人ホーム」を徹底比較|それぞれのメリット・デメリット
■都会で増える親の呼び寄せ問題|同居か?近居か?それぞれの事情と成功のポイント