
離れて暮らす親のことは日ごろから心配なものです。介護が必要になった場合はどうするのか?いざとなった時にあわてないためにも、先々のことを考えておくことが大切です。
遠方に住んでいる親に介護が必要になったとき、遠距離のまま介護を実現するためのポイントをお伝えします。
1.遠距離介護とは?
子が離れて暮らす親のもとに通い、介護、支援しながら親が自宅で生活を続ける介護スタイルのことをいいます。介護の種類は施設介護と在宅介護があります。
在宅介護
家族や介護士などの介護を受け自宅で生活を続けるスタイルのことです(この記事では、子が親と同居しているケースのみを指します)。
遠距離で親をサポートしながら介護する場合に、車で1、2時間くらい離れたとこなら、週末通うこともできるので「在宅介護」も可能です。しかし、新幹線や飛行機を使うとなると頻繁に尋ねることは難しくなります。
介護度にもよりますが、そういった場合は「施設介護」を選択する方が安心と言えるでしょう。
施設介護
有料老人ホーム、特養などの施設に入居し、介護士、医師、看護師などからサービスを受けるスタイルのことです。
遠距離介護は、事前の準備をしっかり行い、必要なサービスを積極的に受けることで実現可能です。いざというときにスムーズに介護をスタートするための知識を得ておきましょう。
2.親が元気なうちに準備しておくこと
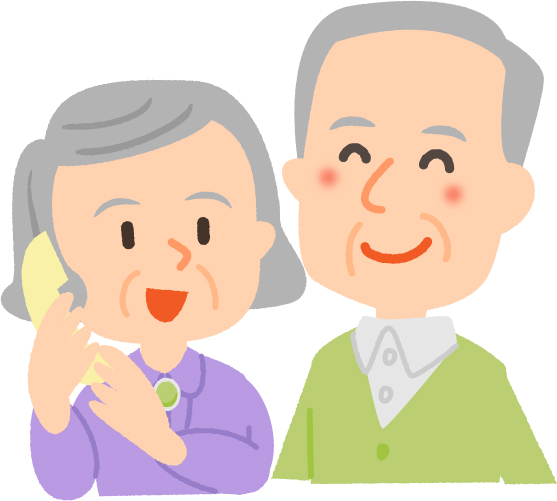 遠距離介護の場合、子が介護できない日は介護保険の居宅サービスを受ける方法がありますが、そのためには「要介護認定」を受ける必要があります。
遠距離介護の場合、子が介護できない日は介護保険の居宅サービスを受ける方法がありますが、そのためには「要介護認定」を受ける必要があります。
介護認定については、こちらの記事で詳しく解説しています。
■要介護認定の申請から認定までの流れ|不服申し立て・介護度が変わった場合は?
■介護認定調査は何をするの?事前に知っておくべきこと ~親の自尊心も大切に~
突然介護が必要になったときに慌てないよう、準備できることは進めておきましょう。
親が住んでいる地域にある地域包括支援センターを把握しておく
要介護認定を受ける際は、地域包括支援センターなどの介護団体に所属するケアマネージャーに相談することから始まります。支援センターがどこにあるのか、連絡先などを把握しておきましょう。
主治医などに相談しておく
要介護認定を受けるには、主治医の「主治医意見書」が必要となります。日頃から診てもらっている主治医に、介護が必要になった場合には遠距離介護を予定していることを話しておくとよいでしょう。
介護認定調査の受け方、ケアプランの作成など、介護サービスを受けるまでの詳しい流れは、以下のページを参考になさってください。
■親の介護が必要になった時にするべき5つのこと
遠距離介護は、事前の準備と情報収集が何より大切です。親が元気なうちから地域の支援先や制度を確認しておくことで、いざというときに慌てず対応できます。
遠距離介護を続けるのは、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。もし「親を呼び寄せて、もう少し近くで見守れたら…」と感じている方には、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)という選択肢もあります。
サ高住なら、見守りや安否確認の体制が整っており、食事や医療のサポートも受けられるため、離れて暮らす家族にとっても安心です。
東京や神奈川など首都圏では、「親世帯を呼び寄せて近居する」スタイルでサ高住を選ぶ方が増えています。
→ 安心して暮らせるサ高住を探す
次の記事では、遠距離介護を続けるうえで知っておきたいメリット・デメリット、そして無理なく続けるコツをご紹介します。
■遠距離介護のメリット・デメリット|無理なく続けるためのコツ
(文:グッドライフシニア編集部 ライター大野 道代)
■介護保険料を滞納するとどうなる?どんな罰則が待ち受けるかを解説
■介護認定調査を受けるに当たり知っておくべきこと ~親の自尊心も大切に~
■「サ高住」と「有料老人ホーム」を徹底比較|それぞれのメリット・デメリット
■一人暮らしをする老親が心配!でも同居が難しい場合どうする?
■都会で増える親の呼び寄せ問題|同居か?近居か?それぞれの事情と成功のポイント



