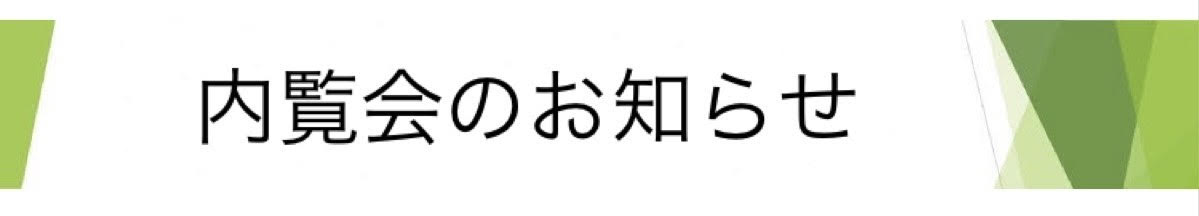老後のお金のことを心配に思っている夫婦は多いのではないでしょうか?老後の生活資金で困らないようにするためには、年金制度への理解を深めておくことが大切です。
しかし、将来の年金受給額を把握している方は、まだまだ少ないのが現状です。また、年金受給額は夫婦の働き方によって大きく異なってくるため、さまざまなパターンを理解しておく必要があります。
本記事では夫婦の年金受給額を、事例を交えつつ解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1.年金受給額の目安を知ることが大切
自分が将来受給できる年金はいくらになるのか、できるだけ正確に把握しておきたいところです。
しかし、年金の計算方法は複雑で、収入や働き方によって基準が異なるため、正確な金額を算出するのは困難です。
さらに、2002年(平成14年)に老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられたように、制度そのものが将来変更される可能性もあります。そのため、現時点で算出した金額がそのまま将来必ず受給できるとは限りません。
とはいえ、年金受給額の目安を知ることは決して無駄ではありません。正確な金額が出せなくても、おおよその水準や平均額を把握しておくことで、老後の資金計画を考える際の参考になります。
2.夫婦の年金受給額の平均額はどのくらい?

では、夫婦の年金受給額の平均額はどのくらいなのか、働き方のパターン別に考えていきましょう。ただし、年金受給額を考えるためには、前提として公的年金制度の仕組みを知っておく必要があります。
重要なポイントを以下にまとめるので、公的年金制度のことをよく理解できていない方は参考にしてください。
公的年金の仕組み
公的年金は「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2階建て構造になっています。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度で、老後に基礎的な年金を受け取るための土台となります。
厚生年金は会社員や公務員が加入する制度で、国民年金に上乗せして支払う仕組みです。
厚生年金の加入者は国民年金の「第2号被保険者」となり、その扶養配偶者は「第3号被保険者」、自営業やフリーランスなどは「第1号被保険者」に区分されます。
また、老齢厚生年金は65歳から支給されるのが原則ですが、1957(昭和32)年4月1日以前生まれの方には60~64歳の間に支給される「特別支給の老齢厚生年金」があります。
特別支給の老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」で構成されており、報酬比例部分は在職中の給料に比例し、定額部分は加入月数に応じて決まります。
65歳以降は報酬比例部分のみとなり、定額部分は老齢基礎年金に引き継がれます。
夫婦の年金受給額の平均額
公的年金制度の仕組みを踏まえたうえで、夫婦の年金受給額の平均額を考えていきます。
以下に会社員、公務員、自営業、主婦などを組み合わせ、大まかな夫婦の年金受給額(月額)を5パターン算出したので、参考にしてみてください。
パターン①会社員(夫)×専業主婦(妻)
| 夫婦年金額 :(夫)約15.0万円+(妻)約6.7万円=約21.7万円 | ||
|---|---|---|
| 夫の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:約8.3万円 ・合計:約15.0万円 |
|
| 妻の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:なし ・合計:約6.7万円 |
|
※国民年金は夫婦ともに20歳から60歳になるまでの全期間保険料を納めた場合(令和6年度:年額804,200円を基準)。夫の厚生年金は平均年収500万円程度で40年間勤務した場合。
パターン②会社員(夫)×会社員(妻)
| 夫婦年金額:(夫)約15.0万円+(妻)約13.3万円=約28.3万円 | ||
|---|---|---|
| 夫の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:約8.3万円 ・合計:約15.0万円 |
|
| 妻の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:約6.6万円 ・合計:約13.3万円 |
|
※国民年金は夫婦ともに20歳から60歳になるまでの全期間保険料を納めた場合(令和6年度:年額804,200円を基準)。夫の厚生年金は平均年収500万円程度で40年間勤務した場合。妻の厚生年金は平均年収450万円程度で35年間勤務した場合。
パターン③公務員(夫)×公務員(妻)
| 夫婦年金額:(夫)約15.0万円+(妻)約13.3万円=約28.3万円 | ||
|---|---|---|
| 夫の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:約8.3万円 ・合計:約15.0万円 |
|
| 妻の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:約6.6万円 ・合計:約13.3万円 |
|
※国民年金は夫婦ともに20歳から60歳になるまでの全期間保険料を納めた場合(令和6年度:年額804,200円を基準)。夫の厚生年金は平均年収500万円程度で40年間勤務した場合。妻の厚生年金は平均年収450万円程度で35年間勤務した場合。
※公務員の公的年金は、2015年(平成27年)に共済年金が厚生年金に一元化され、現在は会社員と同じ仕組みとなっています。
パターン④自営業(夫)×会社員(妻)
| 夫婦年金額:(夫)約6.7万円+(妻)約13.3万円=約20.0万円 | ||
|---|---|---|
| 夫の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:なし ・合計:約6.7万円 |
|
| 妻の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:約6.6万円 ・合計:約13.3万円 |
|
※国民年金は夫婦ともに20歳から60歳になるまでの全期間保険料を納めた場合(令和6年度:年額804,200円を基準)。妻の厚生年金は平均年収450万円程度で35年間勤務した場合。
パターン⑤自営業(夫)×専業主婦(妻)
| 夫婦年金額:(夫)約6.7万円+(妻)約6.7万円=約13.4万円 | ||
|---|---|---|
| 夫の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:なし ・合計:約6.7万円 |
|
| 妻の受給額(月額) | ・国民年金:約6.7万円 ・厚生年金:なし ・合計:約6.7万円 |
|
※国民年金は夫婦ともに20歳から60歳になるまでの全期間保険料を納めた場合(令和6年度:年額804,200円を基準)。
国民年金の計算式
次に、国民年金の計算方法を簡単に説明します。国民年金は以下の式で算出されます。
※満額(804,200円)は令和6年度(2024年度)時点の年額
20歳から60歳までの40年間、全期間保険料を納めた場合は満額受給となり、年間804,200円(月額にすると約67,000円)を受け取ることができます。
今回ご紹介した夫婦のケースは、すべて満額受給できる前提で算出していますが、実際には未納期間や免除期間がある方も多く、満額に届かないケースも少なくありません。
そのため、ご自身が将来いくら受給できるのか、事前に確認しておくことが大切です。
厚生年金の計算式
一方、厚生年金の計算式は以下のようにやや複雑です。
・平均標準報酬額(≒平均月収+賞与) × 5.481/1000 × 2003年4月以降の加入月数
給与や賞与が高いほど保険料も多く納めることになりますが、その分、将来の年金額も増える仕組みです。
厚生年金については、毎年届く「年金定期便」やオンラインの「ねんきんネット」で確認しておくと安心です。
働き方パターン別の年金の毎月の不足額は?
それでは、ゆとりある生活を送るには、いったいどのくらいの金額が必要なのでしょう。
必要な生活資金はその人のライフスタイルによって変わるため、一概には言えませんが、公益財団法人生命保険文化センターが行った意識調査によると、老後の最低日常生活費は月額で平均22.1万円、ゆとりある老後生活費は平均36.1万円と発表されています。
出典:公益財団法人生命保険文化センター「老後の生活費はいくらくらい必要と考える?」
以下の表では、年金だけではどのくらい不足するのかを見てみましょう。
パターン2の夫婦がともに会社員、パターン3の夫婦が共に公務員の方はぎりぎり年金が不足する程度ですが、それ以外のパターンはかなり不足額が多くなります。
| パターン①(会社員×専業主婦) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゆとりある生活費 36.1万円 |
- | 夫婦の年金額 21.7万円 |
= | 不足額 14.4万円 |
| パターン②(会社員×会社員) | ||||
| ゆとりある生活費 36.1万円 |
- | 夫婦の年金額 28.3万円 |
= | 不足額 7.8万円 |
| パターン③(公務員×公務員) | ||||
| ゆとりある生活費 36.1万円 |
- | 夫婦の年金額 28.3万円 |
= | 不足額 7.8万円 |
| パターン④(自営業×会社員) | ||||
| ゆとりある生活費 36.1万円 |
- | 夫婦の年金額 20.0万円 |
= | 不足額 16.1万円 |
| パターン⑤(自営業×専業主婦) | ||||
| ゆとりある生活費 36.1万円 |
- | 夫婦の年金額 13.4万円 |
= | 不足額 22.7万円 |
老後に必要な金額の希望と現実

年金受給額のおおよその目安は把握できたのではないでしょうか。
しかし年金受給額がわかっても、実際、老後の生活にどのくらいのお金がかかるのかがイメージできなければ、ご自身の年金受給額が足りているのか不足しているのか、判断のしようがありません。
今回求めた計算では、金額がもっとも高いパターン②のケース(夫婦ともに会社員)でも、月額は約28.3万円です。
したがって、ゆとりある老後生活を送りたい方は、公的年金以外に収入を得る手段(資産運用や就労など)があるでしょう。
近年、年金に関する問題はよく耳にするようになりました。
老後の夫婦が理想的な生活を送れるようにするためには、将来受給できる年金と不足額の目安を前もって知り、対策を立てておくことが重要です。
実際に老後を迎えてからでは手遅れになってしまう可能性があるので、現役世代のうちに考えておくことをおすすめします。
楽しく充実した老後生活が送れるよう、今回ご紹介した内容を参考にしていただき、ぜひ夫婦で真剣に話し合ってみてください。
年金についての詳しい記事は、年金制度、その種類と仕組みや特徴をご覧ください。
 筆者:伊野文明
筆者:伊野文明宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。元作家志望であり、落ち着いたトーンの文章に定評がある。
■知らないと損をするかも!! 年金請求書が届いた時の「特別支給の老齢厚生年金」に関する注意点
■高齢者世帯の平均貯蓄額はいくら?求められる老後の資金計画
■年金請求・特別支給の老齢厚生年金について解説
■iDecoとつみたてNISAを徹底比較!老後の資金作りを考える