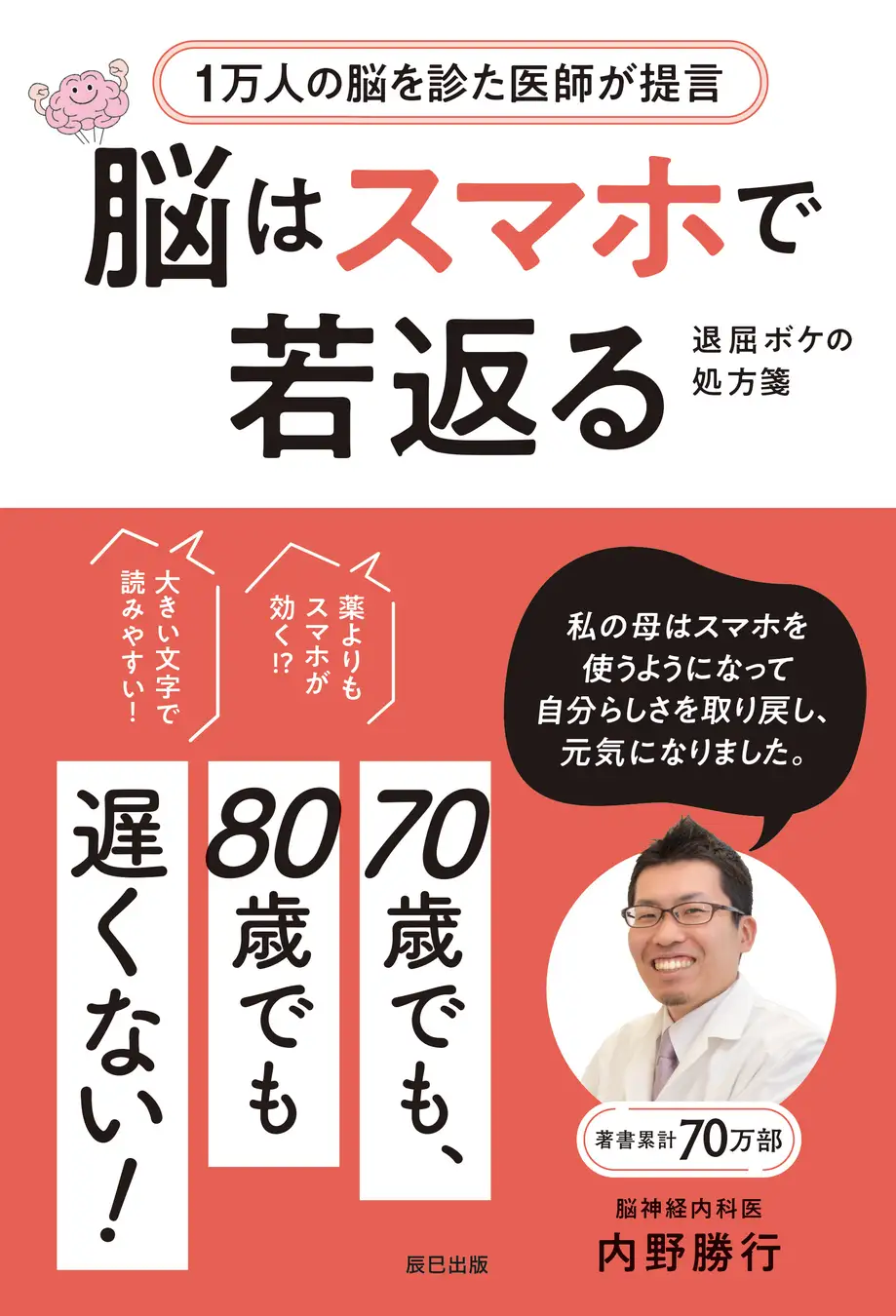近年、定年後も仕事を続けるシニア世代が増えています。将来は年金と給与の両方を組み合わせて生活したいと考える人も多いでしょう。
そこで知っておきたいのが、「在職老齢年金」という制度です。
「在職老齢年金」の対象となると、受け取る給与額によっては年金が減額または受給停止となる可能性があるので、制度の仕組みを理解して、自分に適した働き方を考えなければなりません。
本記事では、受給に関する注意点や年金支給月額の計算法など、分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 在職老齢年金制度とは
「在職老齢年金」は60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら会社に在職して働く方を対象とした制度です。この制度の対象になると、会社の給与と老齢厚生年金の合計が一定の水準を超えた場合、厚生年金が減額または全額支給停止されることになります。
2022年度(令和4年度)に制度が見直され、60~64歳の支給停止基準額が28万円から47万円に段階的に引き上げられました。2025年度現在は、65歳以上と同様に「51万円」が基準となっています。
制度の仕組みを理解していないと、働き過ぎたために受け取れると思っていた年金が減額されてしまう事態を招く可能性があるため、事前に内容を把握しておくことをおすすめします。
ただし、本制度で減額や支給停止の対象となるのは老齢厚生年金であるため、国民年金は対象外であることを覚えておきましょう。
2. 60歳以降の働き方への影響
 >
>
60歳以上で制度の対象となった方が老齢厚生年金を満額受給するためには、給与と厚生年金の合計が定められた金額未満に収まるように調整する必要があります。
在職老齢年金制度では、年金支給がされる基準額は「給与と年金の月額合計が51万円以下」と定められており、51万円を超える場合は、年金支給月額の半分が減額されます。このため、60~64歳の方も給与と年金の月額合計が51万円を超えなければ、老齢厚生年金を満額受給できます。
制度改正の目的としては、60~64歳の方の勤労意欲や仕事へのモチベーション向上があるものと考えられます。
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の求め方を計算式で表すと、以下の通りです。
⇓⇓⇓
全額支給
⇓⇓⇓
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
※日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」より引用
※基本月額は老齢厚生年金の年額を12で割った金額。(加給年金は除く)
※総報酬月額相当額は標準報酬月額に直近1年間の賞与額を12で割った額を足した金額。
したがって、老齢厚生年金を満額受給するためには「給与と厚生年金の合計が51万円を超えるか超えないか?」を意識しなければなりません。
3. 給与+年金の計算例
では、実際に老齢厚生年金を満額受給しながら働く場合、どの程度の給与が上限金額になるのか、平均的な事例として以下を用いて計算してみます。
年金の平均額はどのくらい?
計算をする前に、現在の日本における年金の平均受給額がどのくらいなのか、考えてみましょう。
現在、老齢厚生年金を受給できる年齢は65歳以降となっていますが、65歳以上の厚生年金保険加入者の年金平均月額は約14.5万円となっています。
ただし、年金は国民年金(基礎年金)と厚生年金の「2階建て」となっています。在職老齢年金で減額または受給停止となるのは、厚生年金部分のみなので、国民年金部分は給与の額にかかわらず満額受給が可能です。
国民年金は20歳から60歳までの40年間(480か月)すべての期間に保険料を納めた場合、2025年度(令和7年度)の満額は年額831,696円となり、月額にすると約69,308円(約6.9万円)になります。
そのため、年金の総額が月額14.5万円の方であれば、6.9万円が国民年金(老齢基礎年金)分、残りの7.6万円が厚生年金分という内訳になります。
ただし、国民年金はすべての方が満額納付しているとは限らず、過去に未納や免除期間がある場合は支給額が6.9万円を下回る可能性があります。
厚生年金を満額受給するための給与上限額
前述した平均額を踏まえ、給与の限度額を計算してみましょう。
在職老齢年金制度により、年金支給がされる基準額は「給与と厚生年金の月額合計が51万円」であるため、以下の計算により給与の限度額を求められます。
ここでは計算の便宜上、厚生年金は8万円、国民年金を全期間納めたケースを前提として進めます。
このケースでは43万円が老齢厚生年金(月額)を満額受給するための給与の限度額になります。
実際にはここから税金や社会保険など差し引かれるため、手取り額はやや少なくなりますが、公益財団法人生命保険文化センターの発表では、ゆとりある老後生活費の目安は平均36.1万円程度とされていることから、税金の分を考慮しても十分ゆとりのある収入といえるでしょう。
一方、もし給与と厚生年金の合計が51万円を超える場合は、その超えた分の半額が、老齢厚生年金から差し引かれることになります。
例えば、厚生年金が月8万円、給与が月45万円だった場合
53万円 − 51万円(支給基準額)= 2万円(オーバー分)
2万円 ÷ 2 = 1万円(減額される金額)
8万円 − 1万円 = 7万円(実際の厚生年金支給額)
したがって、この場合では本来8万円受給できるはずの老齢厚生年金の受給額が7万円となり、1万円が減額された結果になります。
この事例では会社の給与を多く受け取ったために損をしたように見受けられますが、中には給与の額が非常に大きい方や、そもそも受給できる厚生年金額が少ない方など、減額になっても影響が少ないケースもあります。
どの程度働き、どの程度の給与を受け取るのが望ましいかは、個人ごとに異なるため、実際の受給額と給与のバランスをよく把握したうえで判断することが大切です。
まとめ
高齢者の就労は今後さらに増えていくことが予想されますが、年金を受給しながら働くこともあるため、年金に関係する制度をよく把握しておくことが大切です。
特に在職老齢年金は制度そのものを知らない方が少なくありません。
在職老齢年金を理解していなければ、給与を多く得ることを重視するあまり、本来得られるはずだった厚生年金が減額されてしまう可能性もあります。そのため、あらかじめ自分が受給できる年金額を把握したうえで、適切な働き方を考えるようにしましょう。
参照:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/index.html
 筆者:伊野文明(いの・ふみあき)
筆者:伊野文明(いの・ふみあき)宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。元作家志望であり、落ち着いたトーンの文章に定評がある。
関連記事
・年金制度とは?その種類や仕組みを分かりやすく解説
・年金(国民年金・厚生年金)の平均受給額はどのくらい?
・夫婦の年金受給額をさまざまなパターンから比較する
・知らないと損をするかも!! 年金請求書が届いた時の「特別支給の老齢厚生年金」に関する注意点
・年金にも税金がかかるの?
・年金制度の改正でどう変わる?改正点について解説!
・お金の不安を減らす「障害年金」の基本を知っておこう