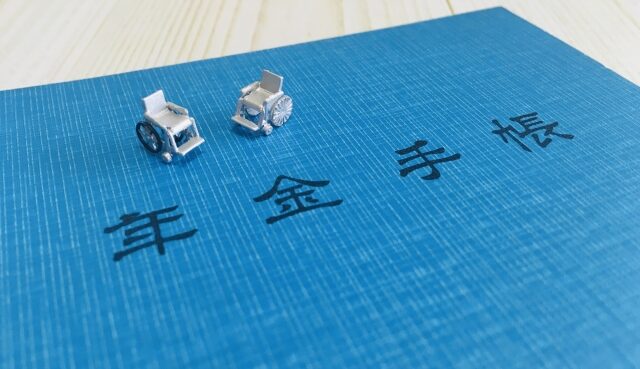
「病気や事故で障害を負い、十分に働けなくなったら…」。そんなピンチに頼りになるのが障害年金です。
障害年金は、障害のない人にとっては存在感が薄く、誤解も多い制度です。でも、障害を抱えた新しい人生にとって、とても大きな支えとなるものです。そんな頼れる障害年金の基本や誤解を解説します。
≫障害年金には2種類(障害基礎年金・障害厚生年金)ある
≫障害基礎年金とは?
≫障害厚生年金とは?
≫障害年金にまつわるよくある誤解
≫障害年金を受給するための3つの条件
≫申請先と必要書類は?
障害年金には2種類(障害基礎年金・障害厚生年金)ある
障害年金は、病気やケガで一定の障害が残り、十分に働けなくなった場合に、国から支給されるお金です。老後の生活を支える「老齢年金」、働き手を亡くした場合に遺族が受け取れる「遺族年金」と同様の、公的年金のひとつです。
障害年金には、障害の程度が重いものから、1級、2級、3級の等級があります。それぞれの障害の程度は、年金法によって次のように定められています。
<障害年金が支給される障害の程度>
| 障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 1級 | 介助がなければ、日常生活のことがほぼできない |
| 2級 | 常に介助を必要とはしないが、日常生活に大きな制限がある |
| 3級 | 労働に大きな制限がある |
| 障害手当金 | 3級よりも軽い程度の障害が残り、労働に制限がある状態(一時金) |
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つの種類があります。どちらに該当するかは、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度で異なってきます。
つまり以下のように、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受け取れます。
| 障害等級 | 国民年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金(1級)+子の加算 | 障害厚生年金(1級)+配偶者の加給年金額 |
| 2級 | 障害基礎年金(2級)+子の加算 | 障害厚生年金(2級)+配偶者の加給年金額 |
| 3級 | 障害厚生年金(3級)(最低保障額年額約58万円) | |
| 障害手当金 | 一時金(最低保障額約120万円) |
障害基礎年金とは?
自営業者や学生、厚生年金に加入中の夫(妻)に扶養されている妻(夫)などが対象となります。受け取ることができる障害年金は、1級と2級のみです。
障害の程度が重い1級のほうが、2級よりも支給される額が多くなり、1級は約97万円、2級は約78万円です(以下、金額は令和4年度)。
さらに、18歳になった後の3月末までの子ども、または、20歳未満で一定の障害のある子どもがいる場合は、「子の加算」(第2子までは年額約22万円、第3子以降は約6万円)がプラスできます。何かとお金がかかる子育て世代にとって、大きな助けとなるお金です。
(例):妻と小学生の子ども2人がある自営業者(月額)
| 1級 | 2級 |
|---|---|
| 約12万円 | 約10万円 |
障害厚生年金とは?
会社員や公務員が対象となり、受け取ることのできる障害年金は、1級、1級、3級、障害手当金です。
1級または2級に該当したときは、障害基礎年金(子の加算も)に障害厚生年金を上乗せした2階建てで支給されます。さらに、一定年収以下の65歳未満の配偶者がいるときは、「配偶者加給年金額の加算」(年額約22万円)がプラスできます。
一方、3級には配偶者加給年金額の加算はなく、障害基礎年金も支給されません。2階建ての2階部分のみとなります。金額は、収入や保険加入月数によって一人ひとり異なります。あくまで目安として参考にしてください。
(例):厚生年金加入期間15年で平均年収が400万円、配偶者と小学生の子ども2人がいる場合(月額)
| 1級 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|
| 約20万円 | 約17万円 | 約5万円 |
障害年金にまつわるよくある誤解

その認知度の低さから誤解も多い障害年金。そんなよくある誤解をご紹介します。
若いから対象外?
「年金=高齢者」のイメージが強く、「若い人はもらえない」と思い込んでいる方もいらっしゃいます。しかしそれは、「老齢年金」の話。障害年金は、20歳から原則65歳になるまでの人が請求できます。
障害年金=障害者手帳?
「障害者手帳を持っていないから、障害年金はもらえない」「障害者手帳で4級だから3級までしかない障害年金はもらえない」。よく聞く勘違いです。
例えば、障害者手帳は「身体障害者福祉法」などの法律などに基づき運用されているのに対し、障害年金は年金法という法律で定められています。
このように障害者手帳と障害年金は、あくまで別制度です。障害者手帳がなければ障害年金を受け取れないということはありませんし、認定基準も異なりますから、等級も必ず同じになるというわけではありません。
うつ病やがん、若年性認知症は対象外?
「障害年金=身体障害者」のイメージが強いため、あまり知られていませんが、うつ病や若年性認知症、がんでも対象となることがあります。
障害年金は、このほか、多くの傷病が対象となります。それは、障害年金は基本的に傷病名ではなく、日常生活や仕事にどのくらい支障があるかで判定されるからです。
「自分は対象外だろう」と自己判断や周りの意見だけであきらめず、自分でしっかりと調べる、もしくは年金事務所や障害年金に詳しい社労士に相談するなどの姿勢が求められます。
障害年金を受給するための3つの条件
障害年金を受給するには、①初診日に公的年金(国民年金や厚生年金)に加入していること、②年金保険料を規定以上納めていること、③障害認定日(障害の程度を決める日)の症状が基準にあてはまること、という3つの条件をクリアする必要があります。
例えば、自分で年金を納める自営業者にありがちですが、①と③をクリアしていても、②の保険料を規定以上納めていなかった場合には、受け取ることができません。
申請先と必要書類は?
障害年金を受け取るためには、申請手続きが必要です。申請先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。障害基礎年金の場合は、市役所でも手続きができます。
そこで年金請求書と必要書類を提出します。年金請求書は住所地の市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターの窓口にあります。必要書類は、障害によって異なるため、年金事務所や市役所などに相談してください。
障害年金は、老齢年金のようにお知らせがきたりしません。自分から動く必要性の高い制度です。突然の人生の変化への助けとなるよう、心の片隅に留めておいてください。
出版社勤務後、フリーランスのライターに。「難しいお金のことをわかりやすく」を目指して日々勉強中。保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士。
年金に関する記事
■年金(国民年金・厚生年金)の平均受給額はどのくらい?
■知らないと損をするかも!! 年金請求書が届いた時の「特別支給の老齢厚生年金」に関する注意点
■年金にも税金がかかるの?
年金制度の改正でどう変わる?改正点について解説!
■夫婦の年金受給額をさまざまなパターンから比較する
■高齢者世帯の平均的な年金収入や貯蓄はいくら?老後に求められる資金計画



