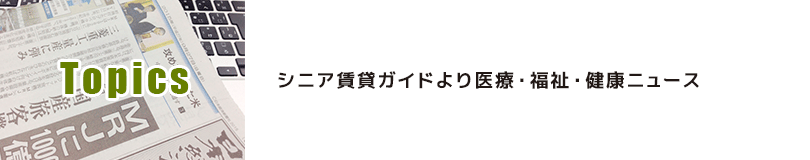国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の世帯数の将来推計」によると、少子高齢化と核家族化の影響により、今後の日本の世帯構造は大きく変化していくと予測されます。
本記事では、その注目すべきポイントについて分かりやすく解説します。
2045年以降、全国的に世帯総数が減少
人口推計によると、2045年以降、全国的に世帯総数が減少に転じるとされています。
2050年には、全国47都道府県のうち40道府県で、2020年時点より世帯数が減少すると予測されます。一方で、東京、沖縄、千葉、埼玉、愛知、神奈川、滋賀では増加が見込まれています。
平均世帯人員が2人未満、小規模世帯が主流に
2020年時点で、平均世帯人員が2人未満だったのは東京だけでした。
しかし、2040年には26都道府県、2050年には34都道府県で平均世帯人員が2人を下回ると予測されています。
特に、2050年には東京と北海道が1.78人と最も少なくなる一方、山形県は2.15人と最も多い値を維持します。
単独世帯の割合が40%以上に
単独世帯の割合は増加が続き、2030年までは全ての都道府県で増加すると予測されています。
その後は減少する地域もありますが、2050年には全国32道府県で単独世帯数が2020年を上回ると見込まれています。
特に東京都では単独世帯の割合が54.1%と全国で最も高く、全国平均でも27都道府県で40%以上に達する見込みです。
75歳以上の単独世帯が倍増する地域も
65歳以上の単独世帯は、2020年から2050年にかけて急増すると予測されています。
特に、沖縄、滋賀、埼玉、茨城の4県では2020年比で2倍以上に増加する見込みです。
また、75歳以上の独居率(単独世帯の割合)は全国的に上昇し、2050年には8都府県で30%以上になると予測されています。
まとめ
日本の世帯構造は、少子高齢化や都市集中の影響を強く受けています。
単独世帯や高齢者世帯の増加、世帯総数の減少は、地域社会や福祉政策に深刻な影響を及ぼしています。
高齢者の単独世帯が急増した地域では、持続可能な地域づくりが必要です。
支援や地域コミュニティとの連携を通じて、社会全体で支え合える仕組みを構築していくことが求められています。
参考:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)-令和6(2024)年推計-」
(グッドライフシニア編集部 松尾)
 旭化成「ヘーベルVillage」は、60歳以上のシニアが安心快適に暮らせるサービスの付いた賃貸住宅です。
旭化成「ヘーベルVillage」は、60歳以上のシニアが安心快適に暮らせるサービスの付いた賃貸住宅です。■旭化成「ヘーベルVillage」、その魅力とは?
■首都圏の「ヘーベルVillage」一覧ページ2025年1月20日
高齢者独居に関連する記事
■一人暮らしをする老親が心配!でも同居が難しい場合どうする?
■都会で増える親の呼び寄せ問題|同居か?近居か?それぞれの事情と成功のポイント
【体験談】親を呼び寄せるべきか?子どもが親の田舎に戻るべきか?