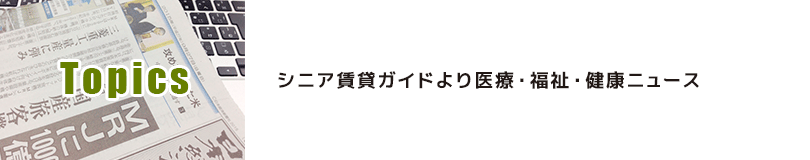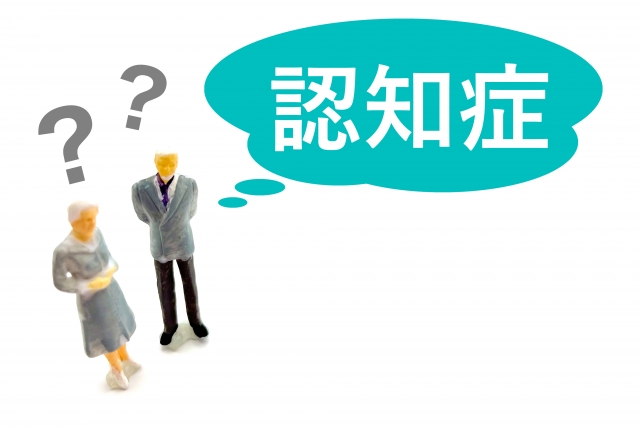
厚生労働省によると、2025年には65歳以上の約5人に1人(約700万人)が認知症になると予測されています。
ひとことに「認知症」といっても、その原因や症状、予防法はさまざまです。
正常と認知症の中間の状態である「軽度認知障害(MCI))」の場合、物忘れはあるものの日常生活に支障はありません。そのうち、年間10~30%が認知症に進行し、一方で5年後に38.5%が正常化したという報告もあり、回復する人もいます。
そのため、認知症は早期診断・早期対応がとても重要となります。また、親が認知症になった場合、成年後見制度などの社会の力をうまく頼って、家族だけで抱え込まないことも大切です。
認知症になると理解力は衰えますが、感情はしっかり残っているといわれています。そのため、本人は変わりゆく自分に、誰よりも戸惑い不安に感じているでしょう。
こちらのページでは、認知症の兆候や性格との関連性、原因や予防法など、認知症について知っておきたいことをご紹介します。
≫1.認知症の原因と予防法
≫2.認知症の主な兆候
≫3.認知症になりやすい人、なりにくい人
≫4.認知症の人は嘘をつく!? その嘘には深いヒミツが
≫5.自宅でできる認知症リハビリテーション
≫6.認知症と間違えやすい「老人性うつ」
≫7.家で出来るコミュニケーション法「ユマニチュード」
≫8.「成年後見制度」とは
1.認知症の原因と予防法
 認知症を引き起こす代表的な病気は、アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)と脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)の4つといわれています。
認知症を引き起こす代表的な病気は、アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)と脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)の4つといわれています。
残念ながら、これらの病気の根本的な治療法は、まだ発見されていません。したがって、発症の予防や進行を遅らせるための早期発見がとても大切になります。
まだまだあやふやな部分が多い認知症。いくら予防をしていても、誰もがなる可能性があります。
こちらのページでは、認知症の具体的な予防策として、運動や食事について詳しく解説します。また、発症したときに頼りになる相談機関もあわせてご紹介します。
詳しい記事⇒■認知症とは?原因と予防法(運動・食事)
2.認知症の主な兆候
高齢の親の言動に気になる部分が増えてきても、「年齢のせいかな?」と見逃しがちなのが認知症です。
目を背けたいという思いもあるかもしれませんが、進行を遅らせるためにも、トラブルを回避するためにも、初期のうちにきちんと医師に診断してもらうことが大切です。
医師の診断をもとに、医療や介護の力で早期に対応することができます。そして、認知症と付き合いながら自分たちらしく暮らす方法をじっくり考える余裕もできるはずです。
認知症の兆候について、普段の行動や会話から気付けるポイントを、具体例とともに解説します。また、離れて暮らす家族が気付けるポイントについても触れていますので、ご参考にしてください。
詳しい記事⇒見逃さないことが大切!認知症の主な兆候とは
3.認知症になりやすい人、なりにくい人
認知症の発症と性格の関係について、さまざまな研究が行われています。性格には「外向性」「調和性」「誠実性」「開放性」「神経症傾向」という5つの傾向があり、それぞれ認知症になるリスクが高い性格、逆にリスクが低い性格に分けることができるとされています。
あなたや家族はどの正確に当てはまるでしょうか? でもたとえ認知症になるリスクが高い性格に該当したとしても、がっかりしないでください。
性格を変えることは難しいかもしれませんが、ご自分が楽しいと思えることを振り返り、そこから認知症のリスクを減らす生活へシフトすることも可能です。
これは、認知症予防だけでなく、これからの生活を楽しむ大きなヒントにもなるはずです。
こ知らのページでは、具体例も挙げながらご説明します。
詳しい記事⇒性格が関係する!? 認知症になりやすい人、なりにくい人
4.認知症の人は嘘をつく!? その嘘には深いヒミツが
 認知症と言えば、物忘れが激しくなる、帰り道が分からなくて徘徊癖がついてしまったなどの、記憶力低下にともなった症状がよく知られています。
認知症と言えば、物忘れが激しくなる、帰り道が分からなくて徘徊癖がついてしまったなどの、記憶力低下にともなった症状がよく知られています。
一方で怒りっぽい、言い訳や嘘をつくと言った「取り繕い反応」はまだ認知が浅く、周囲の人間を困惑させてしまうことも多いと耳にしました。
本人以外にとっては「それは違う!」というような嘘をついてしまうものの、認知症ゆえに意固地になって謝罪ができなかったり、つじつま合わせがうまくいかなかったりと、周りとの軋轢が生まれてしまうのが、この「取り繕い反応」の欠点なのです。
では、認知症を患った本人はこの「取り繕い」についてどう思っているのでしょうか。
今回は、認知症の方がついてしまいやすい嘘をテーマに、良好な関係を築くポイントをご紹介いたします。
詳しい記事⇒認知症の人は嘘をつく!? その嘘には深いヒミツがあった
5.自宅でできる認知症リハビリテーション
現在の医療では、一度認知症を発症すると完治することは難しいですが、認知症におけるリハビリを行うことで、症状の進行を防ぐ、進行のスピードを遅らせることは可能です。
認知症の方は、記憶力の低下などから自信を無くし、自分の殻に閉じこもりがちになることもよく見られます。
そのため認知症のリハビリには、生活にメリハリをつくり、活動意欲を向上させることも期待されています。
このページでは、音楽療法やアニマルセラピー、アロマセラピーなど、自宅で簡単に、楽しく取り組めるリハビリテーションをご紹介しています。
詳しい記事⇒自宅でもできる!認知症リハビリテーションのすすめ
6.認知症と間違えやすい「老人性うつ」
65歳以上の高齢者がわずらううつ病を「老人性うつ」といいます。
配偶者などの大切な人との死別や退職による生活の変化など、老人性うつは加齢による身体的な影響だけでなく、さまざまな要因が重なり合って発症するとされています。
この老人性うつを患う人が増えており、平成29年には127万人以上に。
老人性うつは、認知症と見分けるのが難しいとされています。その見分けるポイントを紹介しながら、家族がとるべき対応や予防法をご紹介します。
詳しい記事⇒認知症と間違えやすい「老人性うつ」|その症状、放っておいて大丈夫?
7.家でも出来るコミュニケーション法「ユマニチュード」
 「ユマニチュード」とは、認知症の方とのコミュニケーション法の一種で、「見る」「話す」「触れる」「立つ」の4つを基本として、150種類以上のコミュニケーションをとります。
「ユマニチュード」とは、認知症の方とのコミュニケーション法の一種で、「見る」「話す」「触れる」「立つ」の4つを基本として、150種類以上のコミュニケーションをとります。
ユマニチュードにより、認知症の方に笑顔が戻り感謝の気持ちを言葉で伝えるなど、驚くべき変化が起こることが認知症介護の現場などでは実証されています。
いったいどのような方法で実践するのか、効果とあわせて詳しく説明しています。
詳しい記事⇒認知症の人に笑顔が戻る!家でも出来るコミュニケーション「ユマニチュード」
8.認知症高齢者を守る「成年後見制度」
認知症に関する大きな心配事のひとつが特殊詐欺や悪質商法など詐欺被害です。
また、キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったり、不動産の処分の際に意思確認がとれなかったり……といった財産面や法律面での困りごとが増えることが考えられます。
そこで利用を検討したい制度のひとつが、成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
ここでは、その2種類の違いだけでなく、どちらの制度を利用すべきかのチェックポイントを相談先とあわせてご紹介します。
詳しい記事⇒認知症高齢者を守る「成年後見制度」とは
以上、認知症について知っておきたいことをまとめました。
できる予防法は今からぜひ実践しましょう。そして、認知症は誰もがなり得るものであるという認識を持つことも大切です。
少しずつ情報を集めながら、早期発見・早期対応を心掛けたいものです。
(グッドライフシニア編集部)
■足が悪くて…認知症で… 近くの医院に行けないなら「在宅医」を頼ろう!
■親の介護が必要になった時にするべき4つのこと
■在宅介護の良い点と問題点|限界を感じたときの対処法とは?
■介護保険制度とは?|その仕組みを分かりやすく解説
■要介護認定の申請方法から認定後までの流れ
 積水ハウス「グランドマスト」は、安否確認や緊急時対応など高齢者が安心に暮らすためのサービスの整った賃貸住宅です。レストランも併設、ご夫婦や親子での入居におすすめです。■「グランドマストシリーズ」その魅力とは?
積水ハウス「グランドマスト」は、安否確認や緊急時対応など高齢者が安心に暮らすためのサービスの整った賃貸住宅です。レストランも併設、ご夫婦や親子での入居におすすめです。■「グランドマストシリーズ」その魅力とは?
【入居者の声】サ高住や高齢者向け賃貸に入居した方の生の声を集めました
2021年10月21日