
一般的に介護というと「80代~90代の親を60代~70代の子世帯がお世話をする」老老介護が浮かびます。しかし最近では、60代以下の家族をその配偶者や、家族が面倒をみる「若若介護」の問題も浮上しています。
本記事では、若若介護の体験者の声を交えながら、なぜ若若介護が大変なのか、その解決策についてもご紹介します。
≫1. 若若介護とは?ヤングケアラーとの違い
≫2. 若若介護はなぜ大変なのか
≫3. 若若介護は「できるからといって一人で抱え込まない」
≫4. サービスの付いた高齢者向け住宅を検討してみましょう
1. 若若介護とは?ヤングケアラーとの違い
若若介護とは、若い20代〜40代の家族が、50代〜60代の身内を介護することです。また、40代から50代の方が、同年代の配偶者の介護を行う場合も若若介護と言われることがあります。
また、18歳未満の子供が家族の介護を担うケースは「ヤングケアラー」と呼ばれ、社会問題にもなっています。若若介護とヤングケアラーは年齢層こそ異なりますが、いずれも“本来なら介護の担い手とは想定されていなかった世代”が、家族の支え手となる点で共通しています。
本記事では主に30代~50代が親や配偶者を介護する「若若介護」に焦点を当てていますが、介護の負担が若年化している点ではヤングケアラーとも共通する部分があります。
2.若若介護はなぜ大変なのか
- 先が見えない不安
- 生活基盤が揺らぐこともある
- 本人の意思と体の不自由さ
- 子育てと介護の両立
①先が見えない不安
介護を受ける方が50代や60代の場合、一般的な寿命を考えてもかなり長期間の介護となる可能性が高くなります。10年、20年と続くかもしれない介護。
また介護では状態が良くなるより悪くなることが多いのも事実で、終わりのない介護の現場に対する不安が大きくなりがちです。
周囲のママたちが、自分の親に子どもを預けて夫婦で食事に行った、保育園のお迎えはお母さんに頼んでいるなんて話を耳にすると、それどころか親の世話をしに通わなくてはならない自分の身の上を恨みました(Uさん/32歳の時から60歳実母の通い介護へ)
②生活基盤が揺らぐこともある
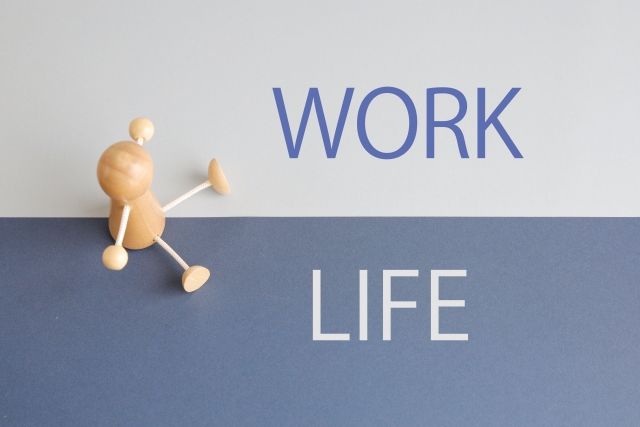
30代から40代といえば、仕事でも責任ある立場になりつつある年代です。しかし介護の程度によっては、早退や遅刻、有給消化が続き、場合によっては転職や退職ということもあり得ます。
派遣やパートに切り替えたために、収入が激減したというケースも。共働き夫婦の片方が仕事を辞めれば、ライフプランそのものが変わってきます。
若年の介護は長引くことも考えられることから、一時的な収入の減少ではなく、生活基盤が崩れるリスクがあるのも若若介護の現実といえるでしょう。
介護の時間を捻出するため、転職を余儀なくされ、収入も減った。老後の生活設計もすべて白紙に。不安ばかりが募る(Tさん/52歳の時2つ年上の妻が若年性認知症になり現在も自宅介護中)
③本人の意思と体の不自由さ
50代前後、あるいはもっと若いときに身体に何らかの不自由が生じると、ご本人としては老化を捉えにくく、苛立ちや不満がふくらんでしまいがちです。
また、意識も意思も明確であることが当初は多く、そのために介護する人に対しても「自分はボケていない」「自分はきちんとやれる」となかなか素直に受け止めてくれないケースもあり、家族間のトラブルが起きやすい面があります。
舅は日ごとに頑固になり、自分を年寄り扱いするなと物を投げつけることもあり、精神的に参っています。現在は地域包括支援センターで相談中で、施設入居を検討しています(Fさん/37歳の時に舅:当時63歳の介護をスタート、3年目に施設入居へ)
④子育てと介護の両立
介護が必要な家族が60代ということは、面倒をみる子世帯は30代から40代です。働き盛りでもあり、子どもがいれば子育てにも忙しい年齢層です。
子育てと介護を同時に行う「ダブルケア」は、非常に大きな負担がかかります。手助けが必要な年代に挟まれた「30代~50代」の家族にとっては非常に厳しい状況です。
でも、自分たちの生活が崩壊してしまったら、それこそ母親の面倒じたいも見られなくなる。母は要支援2ですが、元気な60代夫婦の方もお住まいになっている住宅型の施設で、見た目も老人ホームというよりマンションを見つけ、見学したら気に入った様子で思ったより抵抗感なく入居してくれてホッとしました。
あのまま自宅介護を10年も続けていたら、たぶん自分が倒れていたと思います(Uさん/32歳の時に実母57歳を自宅介護、5年目で施設入居を進める)
3. 若若介護は「できるからといって一人で抱え込まない」

若若介護に限らず、介護の現場ではとにかく「ひとりですべて抱え込まないこと」が大切です。自治体の相談窓口を利用し、地域の包括支援センターも積極的に活用しましょう。
30代や40代は無理をすれば何でもできてしまうかもしれません。しかし、介護は数ヶ月や1年で終わるものではありません。
また子育てのように、成長し、独り立ちしていくステップが見えるわけではなく、そのために介護では心の疲弊も知らずとたまってしまいやすい面があります。
介護は年齢に関係なく、大変なこと。「今はまだ、できる」ではなく、これからのことも考えながら周囲に相談をし、必要な手助けを得るようにしましょう。
4. サービスの付いた高齢者向け住宅を検討してみましょう
介護する側も若く、介護される人も高齢者でないと、施設への入居という選択肢が狭まる傾向があります。
いわゆる老人ホームは少なくとも60歳、65歳以上でないと入れないと思っている方も多いようです。実際にこうした規定のある施設も多くあります。
しかし、介護を受ける人が60歳未満でも入居できるところが増えています。また、サービス付き高齢者住宅の中には、自立した人を対象としつつも、実際にはいわゆる老人ホーム同様の介護サービスを別途契約し利用できるところもあります。
 積水ハウス「グランドマスト」は、安否確認や生活支援など各種サービスのある賃貸住宅です。60歳以上の方が契約者となった場合、介護の必要なご家族(妻・子・姉妹など)が同居することも可能です。
積水ハウス「グランドマスト」は、安否確認や生活支援など各種サービスのある賃貸住宅です。60歳以上の方が契約者となった場合、介護の必要なご家族(妻・子・姉妹など)が同居することも可能です。■「グランドマストシリーズ」その魅力とは? ■お問い合わせ
さらに老人ホームよりも「シニア向け賃貸マンション」と捉えると、ハードルが低くなり、介護される人も受け入れやすいメリットがあります。
ただし、サービス付き高齢者の条件はさまざまです。認知症や特定の疾病では入居できないところもあるので、まずは条件にあった住宅・施設を探してみましょう。
介護する人にも生活があり、その人の人生があるのです。介護する人もされる人も、互いの負担ができるだけ少なくなるようにしたいですね。
 筆者:大橋 礼
筆者:大橋 礼主に教育・ライフスタイルを中心に執筆するフリーライター。自身の介護経験と親世代・子世代両方の視点から取材を行いリアルな声を届ける。サードエイジ世代の新しい暮らしと50代からの豊かな人生を求めて模索中。
若若介護に関連する記事
■介護保険が65歳未満でも使える「特定疾病」|40歳以下が利用できる「障害福祉サービス」
■障害を抱える子が親と同居できる!? 高齢者向け賃貸の意外なメリットとは?
■【親子で住める高齢者向け賃貸】子どもの介護に悩んでいる方へ
■大家さんは社会福祉士!障害をもつ子と親が安心に住める賃貸住宅「ウィステリアハウス」
■【在宅介護か?施設介護か?】あなたはどちらを選択しますか
■増加する「老老介護」「認認介護」の問題点と対策|一人で悩まず周囲に相談を
■要介護1で一人暮らしは続けられるか?認知症の場合はどうする
■要介護2で一人暮らしはできるのか?実際のケースを見ながら解説
■在宅介護の良い点と問題点|限界を感じたときの対処法とは?
■要介護3で一人暮らしはできるのか?実際のケースを見ながら解説
■在宅介護の良い点と問題点|限界を感じたときの対処法とは?
■介護で疲れた!ストレスのサインと介護の負担軽減策



