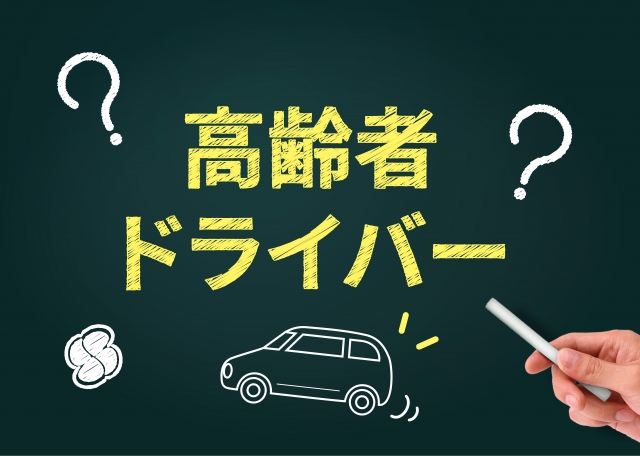
高齢者ドライバーの事故が年々増加傾向にあります。
このページでは、高齢者が事故を起こす主な原因について、また、免許更新時の高齢者講習や認知機能検査、自主返納を考えるタイミングや、自主返納のメリットについてまとめました。
大切な親に安全に運転を続けてもらいたうためにも、家族が知っておきましょう。
増加傾向にある高齢ドライバーの事故、主な原因は?

今でも記憶に刻まれている池袋の乗用車暴走事故。高齢ドライバーの乗用車にはねられ母子が亡くなった痛ましいニュースに多くの方がショックを受けました。
このような事故は、高齢ドライバーの家族を持つ人には決して他人ごとではありません。
通常、自動車事故により他人に怪我を負わせた場合「過失運転致死傷罪」に当たり、車の運転している以上、ドライバー本人に責任能力はあると判断され家族の責任は問われません。
しかし高齢者で認知症が進行している場合は、家族に監督義務が発生します。つまり認知症の親が人に怪我をさせたら、子が責任を負う可能性もあるということになります。
高齢者が事故を起こす主な原因は、安全不確認や前方不注意発見の遅れ、相手の動静への不注意、予測不適による判断の誤り、ブレーキやアクセルの操作ミスなどがあります。
若い人なら運転中にとっさにブレーキを踏むことができます。しかし、高齢者は瞬時に判断する力が低下し、複数の情報を同時に処理することが苦手。
そのため、ハンドルやブレーキ操作にミスや遅れが出るといった特性が見られるようになります。
また、60歳を過ぎると認知機能が少しずつ衰えていくため、年を重ねるごとに認知症の心配も出てきます。
警察庁によると、平成28年の運転免許証更新の際、認知機能検査を受けた75歳以上が約166万人。そのうち約5.1万人は認知機能が低下し記憶力・判断力が低くなる状態「認知症の恐れがある第1分類」と判定されています。
加齢に伴い身体機能の低下に、認知機能の低下も加わり高齢者ドライバーの事故のリスクは上がるのです。
75歳以上の免許更新には認知機能検査も必須
70歳以上になると、免許更新の申請をする前に2時間の「高齢者講習」を受けなければなりません。
75歳以上の人は3時間の高齢者講習の他に、「認知機能検査」の受検も必須となり、受講しないと免許証の更新はできません。
認知機能検査の検査項目は、記憶力や判断力を測定する検査となっており、採点の点数に応じ以下の3つに分類されます。
・「記憶力・判断力に心配ない(認知機能が低下していない)」
・「記憶力・判断力が少し低くなっている(認知機能が低下しているおそれがある)」
・「記憶力・判断力が低くなっている(認知症のおそれがある)」
認知機能検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定された場合には、警察から連絡があり、臨時適性検査、もしくは診断書提出命令により医師の診断を受けることになります。
もし認知症と診断された場合は、聴聞などの手続を経た上で免許の取消し、または効力の停止を受けることとなります。
また、75歳以上で一定の違反行為(信号無視や通行禁止違反など)があった場合も、臨時に認知機能検査を受ける必要があります。
自主返納を考えるタイミング

自主返納は、身体機能の低下などを理由に、まだ有効期限の残っている運転免許を本人の申請により取り消し返納する制度のことです。高齢ドライバーの事故の多発を受けて1988年4月から導入されました。
以下のような症状が出たときには注意が必要です。そろそろ自主返納を考えましょう。
・右左折のウインカーを間違って出したり、出し忘れたりする
・カーブをスムーズに曲がれないことがある
・歩行者、障害物、他の車に注意がいかないことがある
・車庫入れの時、塀や壁をこすることが増えた
親の運転に不安がある方は、1度同乗して運転が大丈夫なのかチェックしてみてはいかがでしょう。
身分証がなくなる心配もありません。免許証を返納した後に5年以内に申請すれば、公的な身分証として利用可能なカード「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。
このカードを提示すれば、タクシーやバスを割引運賃で利用できたり、金融機関の窓口などで本人確認として使用できます。
手続きは管轄の警察署や運転免許センターなどできます。免許証と免許証用サイズの写真を提出し、手数料は1100円です。
また、運転経歴証明書を提示することにより、各自治体が百貨店の宅配料金の割引、美術館、飲食店の料金割引など、さまざまな特典が用意されています。
東京の場合は、日通の引越10パーセント割引、帝国ホテル直営レストラン・バにて10パーセント割引、高島屋は自宅への配送無料、はとバスは定期観光を5パーセント割引など、その他、さまざまな特典があります。
各都道府県の特典については「高齢者運転支援サイト:各種特典のご案内」をチェックしてください。
あわせて読みたい記事
親に免許返納をすすめても、なかなか聞く耳を持ってくれないとお困りのご家族。プライドを傷つけないよう考慮しながら説得する方法を考えてみましょう。
老親に車の運転をやめさせたい!免許の自主返納を説得する方法
参考:政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201804/3.html
運転免許証の自主返納・運転経歴証明書について
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/korei/henno_keireki.html
運転免許証の自主返納に関するリーフレット
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/rdhleaflet.pdf
(グッドライフシニア編集部 松尾まみ)
■「高齢者向け賃貸住宅」ってどんな住まい?「一般賃貸」との違いは?
■都会で増える親の呼び寄せ問題|同居か?近居か?それぞれの事情と成功のポイント
■遠距離介護の親をどう支援すべきか? 事前の準備が大切
■一人暮らしをする老親が心配!でも同居が難しい場合どうする?
【体験談】親を呼び寄せるべきか?子どもが親の田舎に戻るべきか?
 【充実のサービスで生活をサポート!】バリアフリー設計、安否確認や生活相談、レストランでのお食事サービスなど、シニアが安心・快適に暮らすためのサービスを備えた賃貸住宅です。
【充実のサービスで生活をサポート!】バリアフリー設計、安否確認や生活相談、レストランでのお食事サービスなど、シニアが安心・快適に暮らすためのサービスを備えた賃貸住宅です。■「グランドマストシリーズ」その魅力とは?2022年2月24日




