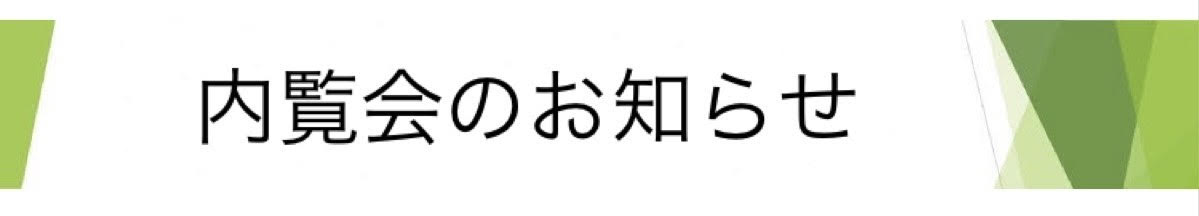東京都健康長寿医療センターの調査によると、高齢者の6割が3疾患以上の慢性疾患を併発しているという結果が出ています。
これらの病気は、生活習慣の積み重ねが原因となり、中年期(30代・40代・50代)からじわじわ進行していくケースも少なくありません。
病気を未然に防ぐためには、日常生活での予防が何よりも大切です。
今回は、「今は体力に自信があるけれど、将来の健康が心配…」という方に向けて、中年期のうちから気をつけたい生活習慣病について、また、運動不足や体重の増加、姿勢など生活習慣が影響することもある病気についてご紹介します。
1. 骨粗しょう症

骨量が減り骨がもろくなった状態になる骨粗しょう症。元気でいきいきとした老後を過ごすためには、骨の健康は欠かせません。
骨がもろくなることで骨折しやすくなり、腰痛を引き起こしたり、将来の寝たきりの原因となったりします。
骨粗しょう症予防には、骨の材料となるカルシウムの摂取が大切です。カルシウムの摂取が不足すると血中のカルシウム濃度が下がってしまい、濃度を維持しようとして骨のカルシウムが取り出されてしまい、骨密度を下げてしまいます。
ほかにも、ビタミンDやビタミンKの摂取、さらには適度な運動も欠かせません。
骨粗しょう症になるかどうかの鍵を握るカルシウムの豊富な食事メニューを筆頭に、効果抜群の体力づくりについてもご説明いたします。
詳しい記事を読む⇩
■骨粗しょう症を予防するには?食事や運動のポイントを管理栄養士が解説
管理栄養士による骨粗しょう症予防に効果的なレシピはこちらから☟
■カルシウムたっぷりスキムミルク入り「和風ハンバーグ」
2. 動脈硬化

コレステロールの値は、「動脈硬化」の進行と深く関係しています。
LDLの中に入って運ばれるコレステロールを「LDLコレステロール(悪玉コレステロール)」、HDLで運ばれるコレステロールを「HDL(善玉)コレステロール」と呼びます。
LDLコレステロールが血管内に溜まると、動脈硬化が進行していきます。
この動脈硬化は、動脈の壁(血管)が硬くなり弾力性が失われた状態のことで、進行すると血管壁にプラークがつき血管内を狭くしてしまいます。
さらに、プラークが破けると血栓となり、血管を詰まらせて狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などを誘引する恐れも。
LDLの数値が上がる原因として、挙げられるのは食習慣。そのほか、肥満や体質、遺伝、運動不足も挙げられます。
ここでは悪玉・善玉コレステロールの違い、コレステロール値の上昇にともなう動脈硬化のリスク、予防のための生活習慣について知っておきましょう。
動脈硬化に関する詳しい記事を読む⇩
■LDL(悪玉)コレステロールは何が「悪」?体への影響を知って動脈硬化を予防しよう
■【管理栄養士が教える】動脈硬化予防の食事や取り入れたい食べ物とは?
■閉塞性動脈硬化症で困る症状は足だけではない?生命予後に血管が関係する
3. 脳血管疾患(脳卒中)
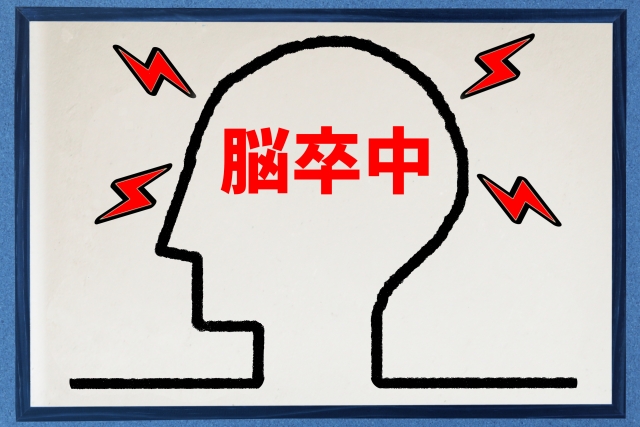
脳血管疾患とは、脳血管のトラブルによって脳細胞が破壊される病気の総称です。さまざまな種類がありますが、最もよく知られているのが「脳卒中」です。
脳卒中には以下の2つのタイプがあります。
・血管が破れることによって生じる「出血性脳血管疾患(脳出血、くも膜下出血)」
・血管が詰まってしまうことで生じる虚血性脳血管疾患(脳梗塞、一過性脳虚血発作)
それぞれの脳血管疾患の症状や原因と予防策、また、「こんな症状が出たら病院へ」といった症状についても解説します。
脳血管疾患に関する詳しい記事⇩
■脳血管疾患(脳卒中)の症状や原因を知って予防を心がけよう
突然病に倒れるイメージの強い脳卒中ですが、高血圧や動脈硬化などの危険因子は何十年も時間をかけて蓄積されています。
脳卒中にならないためのポイントは血管の炎症予防にあります。脳卒中に倒れないための10か条をもとに、若いうちからできる血管の炎症予防を心がけましょう。
医療機関で20年以上勤務してきた経験のある看護師ライターが唱える30~40代からの脳卒中対策について解説します。
脳血管疾患の予防に関する詳しい記事⇩
■脳卒中予防は30代、40代から。食事・生活習慣を見直そう!
4. 糖尿病

インスリンが十分に働かないために、摂取した食物エネルギーを正常に代謝できなくなり、高血糖が慢性的につづいてしまうのが糖尿病です。
糖尿病には大きく分けて、「Ⅰ型糖尿病」「Ⅱ型糖尿病」の2つのタイプがあります。
糖尿病になると、疲れを感じやすくなる、のどが渇く、食欲が増える、足のしびれがあるなど、様々な症状が体に表れるようになります。
糖尿病を予防するには、何と言っても「食生活」と「運動」のコントロールが大切です。
糖尿病に関する詳しい記事⇩
■糖尿病の種類や原因、症状は?生活習慣を見直して予防しよう!
■血糖値を抑える食事法│シニアが知っておきたい4つのポイントとは
管理栄養士による血糖値対策に効果的なレシピはこちら☟
■話題の「オートミール」で作る炒飯
5. 高血圧
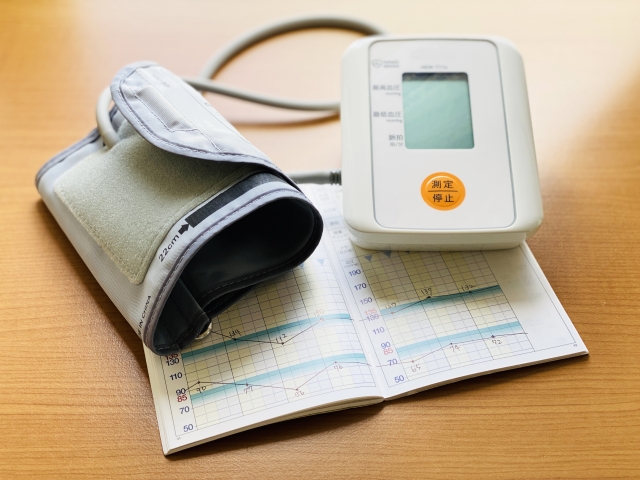
患っているのは自分だけじゃないし、よくある症状だから、と油断してしまいがちな「高血圧」。その正体は、脳血管や心臓の病気につながるリスクのある危険な生活習慣病です。
血圧には上と下の2種類の数値があり、上の血圧は心臓が収縮して血液を送り出す際の数値で「収縮期血圧」、下の血圧は心臓が拡張したときの数値で「拡張期血圧」と言います。
高血圧症と診断されるのは、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合です。
塩分の摂り過ぎや肥満や喫煙、ストレスやなどが主な原因ですが、高齢者の約3分の2が高血圧と言われているほど多い病です。
高齢者の高血圧対策では、若年・中年層とは異なる特有の症状があることを、しっかり押さえておきましょう。
ここでは放っておくと危ない、高齢者の方に特化した高血圧対策についてご紹介します。
高血圧に関する詳しい記事⇩
■放っておくと危ない!高齢者の高血圧(その症状や対策)
6. 腰痛

痛みを伴う身近な病気、悩みといえば腰痛。湿布を貼ったり、痛み止めを飲んでみたりしてみても、なかなか治った感じがしないと悩んでいませんか?
実は腰痛には内臓の疾患が原因のものがあったり、運動習慣で悪化を予防できたり、でも実は腰痛改善に向いていないスポーツもあったりと、知らないことが意外とたくさんあるものです。
大きなストレスにもなる慢性腰痛の原因、改善方法などについてご紹介します。
■腰痛の原因は?改善のカギは日常生活にあった|NGな姿勢・趣味・習慣とは
放置は危険?腰痛のタイプ別に、緊急度や対処法をわかりやすく解説します。
■この腰痛放っておいて大丈夫?痛みのタイプ別、緊急度と対処法
足のしびれや腰の痛みの原因「脊柱管狭窄症」についての記事はこちらから。
■足のしびれや腰の痛みが出る脊柱管狭窄症(症状や治療について)
以上、40代・50代から注意したい6つの病気についてご紹介しました。日常生活の中で少しずつ意識を高め、将来の健康につなげていきましょう。
(グッドライフシニア編集部)
健康・病気予防に関するおすすめ記事
■糖質制限の効果と注意点|ダイエットにおすすめの食べ物やNG食材は?
■食後の眠気は血糖値スパイクかも!?予防するための食べ方・食事の過ごし方とは
■健康的な生活は良い睡眠から!眠りの質を高める方法は?
■もっとも長生きする睡眠時間は?“質の良い眠り”のための7箇条とは
■シニアの虫歯急増!歯の数を減らさない7つのお口ケア
■医者が健康のために食べてる食材TOP5とは?
■栄養バランスの重要性|食生活改善の効果が出る時期はいつ?
■がん予防に効く食べ物10選!科学的に効果が証明された健康食材とは?